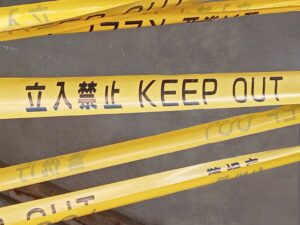“サブスク疲れ”の救世主?――アメリカで急成長する動画配信サービス「FAST」とは何か

米国のネットストリーミングサービスの形態として、「FAST」と呼ばれるものが急速に拡大している。
FASTとは、「Free Ad-Supported Streaming TV」の略で、無料で広告を入れてコンテンツをライブ配信するサービスのことである。
事業としては以前から存在したが、2019年に「FAST」という名称が与えられたことで理解が進み、急速に普及した。
現在はFASTプラットフォームだけで30以上、チャンネル数は3000以上あると言われている。
FASTは、コンテンツをストリーミングするという意味ではVODサービスのように見えるが、ある意味では全く逆のサービスであるとも言える。
米Amazon プライムビデオや米Netflixといったサービスは、まず見たいコンテンツがあり、それを見るために加入するものだ。
一方テレビ放送は、特に何か見たいものがあるわけではないがそれっぽいものを付けていればドラマだったりお笑いだったりニュースだったりが次々にアラカルト的に流れていくので、なんとなく見たという気にさせられる。
考えなくていいメディアだ。
FASTは、このテレビ的な「考えなくていい」という特性をネットに持ち込んだものと言える。
プラットフォーム内には専門チャンネルが並び、それらは番組表に沿ってライブストリームでコンテンツを流し続けている。
巻き戻して最初から見ることはできないが、眺めていれば次々と同じ傾向のコンテンツを流し続けてくれる。
日本で近い感覚のものは、CS放送だろう。
あの専門チャンネル群がネットサービスになって、CM差し込み型の広告モデルとなり、無料で見られるといったイメージだ。
FASTの事業者には、いくつかのパターンがある。
大きく分けると、ハードウェア型とソフトウェア型がある。
ハードウェア型というのは、特定のハードウェアに組み込まれたサービスを指す。
代表的なところでは、「ROKU」がある。
ROKUはいわゆるボックス型やスティック型サービス端末の走りのようなもので、テレビをネットサービス対応にしてくれるデバイスだ。
米国には同様のデバイスが色々あったが、最終的にROKUが生き残った格好だ。
「TiVo+」は、2000年以降に全米で流行したHDDレコーダ「TiVo」が祖業といえば祖業だが、ここは結構複雑な経緯がある。
アナログ時代にコピーガード技術を生み出した「Macrovision」が「Rovi」という番組情報配信サービス会社になり、そこに「Sonic Solutions」とか「DivX」とかが合流していってTiVoもそこに買収されたが、名前としてはTiVoの方が有名だったため社名をTiVoにした…というところまでは2016年ぐらいまで追いかけていたが、その後はどうなったのかは取材が及ばず、正直よくわかっていない。
「Samsung TV+」はSamsungのテレビに、「LG Channels」はLGのテレビに、「Vizio Watch Free+」はVizioのテレビに組み込まれたサービスだ。
一方ソフトウェア系のほうが出自が多彩で、キー局テレビ系、ローカルサービス系、IT系などがある。
キー局系としては、2013年にサービスインしてのちにCBSに買収された「Pluto TV」がある。
ここが現在FASTの中では最大勢力である。
「Tubi」はFoxが買収したサービス、「Peacock」はNBC系列のサービスだ。
IT系では米Amazonが買収した「Freevee」、クラウドサービスベンチャーからスタートした「Plex」がある。
PlexはGoogle系OS搭載のプロジェクタによくアプリが搭載されているので、アイコンぐらい見たことがある人はいるだろう。
これはブラウザでも視聴可能なので、どんなものか体験したい人は日本語のサイトもある。
ただコンテンツの中身が日本語化されているわけではない。
FASTサービスの中身は、ほとんどがテレビ番組として制作されたものの再配信である。
つまりFAST向けに新規コンテンツを制作しているわけではなく、旧コンテンツや現コンテンツが放送以外の経路を通って広告モデルとして配信されるというものだ。
サービスによっては、一部オンデマンド型でシリーズものを配信しているケースもある。いわゆるテレビ向けに制作されたドラマなどだ。それらも広告が入る無料配信モデルとなっている。
FASTサービスの特徴は、特にアカウントを作成しなくても利用できるということである。
広告はコンテンツの合間に挟まれるわけだし、チャンネルごとにユーザーの嗜好情報は取れる。
例えば料理チャンネルを見ている人は飲食に興味がある人だし、キッズチャンネルを見ているのは子どもだ。
それ以上プロファイルを取る必要がない。よって広告も売りやすいし、チャンネルのカラーに合ったものだけが集まるので、キッズチャンネルにアダルトな広告が飛び込むようなことは起こらない。
日本から視聴していると、挟まれる広告はほぼ他のチャンネルや番組の番宣になる。
おそらく地域ごとにCMが管理されているからだろう。
FASTが流行ってもう5~6年になるので、米国ではそれなりになぜウケたのかの分析が進んでいる。
1つの理由は、視聴者の「サブスク疲れ」だ。
米国のテレビ視聴は長らくCATVが中心であり、地上波をアンテナで直接受信している世帯は非常に少ない。
ここが日本と大きく違うところだ。
動画のサブスクサービスが台頭した2010年代頃から、CATVの契約を切ってサブスクに絞るユーザーが出てきた。
ケーブル契約を切るので、これらの人たちは「コードカッター」と呼ばれた。
しかしその代わり、サブスク契約は1つというわけにもいかず、3つも4つも契約する羽目になる。
それぞれの料金は必ずしも安いものではなく、家計を圧迫し始めた。
さらにサブスクサービスは、何を見るか懸命に複数のサービスをブラウジングし、結局何も決められないまま時間だけが過ぎるといった現象を引き起こすようになった。
目の前にあまりにも沢山コンテンツがありすぎても、決められなくなってしまうのだ。
さらに視聴スタイルも異なる。
サブスクサービスは基本的にはビデオレンタルに代わるものなので、コンテンツは映画のように前のめりになって視聴を迫るものが大半である。
テレビ放送のように、カウチにケツを預けてピザをビールで流し込みながら頭を空にして眺めるような、リーンバック型の視聴スタイルとは馴染みが悪い。
毎晩毎晩仕事から疲れて帰ってきてるのにこれは辛い、というわけである。
もっとテレビ的なコンテンツを、タダで見られないのか。
こうしたニーズにFASTがハマった。
もう1つの理由は、サブスクサービスだけだと、ニュースが見られないということである。
米国はテレビニュースへの関心が非常に高く、ネットニュースと併用されている。
全国ニュースはネットでも一部見られるが、ローカルニュースをテレビで見るシステムがない。
先にも述べたが、米国のテレビはほとんどアンテナ線に繋がってないのだ。
これはやはり不便だということで、FASTが提供するニュースチャンネルが注目されるようになった。
3つ目は、コンテンツを提供するテレビ局は、新たにFAST用のコンテンツを作らなくていいということである。
FASTは必ずしも最新のテレビ番組は求められておらず、昔の古いテレビコンテンツがそのまま放映されている。
自分が生まれる前の西部劇や「エド・サリバン ショー」を見たいというニーズはそれなりにあるのだ。
これまでCATVに安く卸すだけだったコンテンツが、また別のところで金を生むようになったわけだ。
ニュースチャンネルは、新たにニュース番組を制作する必要はなく、放送とサイマルで配信すれば済む。
そもそも米国にはニュース専門チャンネルがいくつもあり、24時間ニュースを流し続けている。
つまりFASTは、消費者にとってはもう一度CATVと契約し直す必要はなく、これまで見てきたサブスクの環境があれば、そのまま以前のようなテレビ放送型のコンテンツ視聴体験ができる。
新しい技術を使って古いスタイルに戻れる、しかも無料で、というわけだ。
テレビ局側にとっては、新しくコンテンツを作る必要はなく、今手元にあるものを出せばいい。
元々テレビ番組は間にCMが入るように制作されており、コンテンツにちゃんと切れ目がある。
映画のような切れ目のない作品に無理やりCMをぶち込んで苦情が来るといったこともない。
しかも広告が売りやすい。
それぞれが専門チャンネルなので、チャンネルごとにターゲティングができている。
わざわざリスクを冒して個人情報を取る必要がない。
FASTが米国でウケたのには、いくつもの歯車が噛み合った結果と言える。
こうしたFASTを、日本でもやったらどうか。
特にテレビ離れが進んで困っている地方局には、救世主となり得るのではないか。
そうした議論が数年前から始まっている。
確かにローカル番組やローカルニュースといったコンテンツが、テレビ放送以外のルートで配信でき、そこの広告枠が売れるのならば、魅力的な話ではある。
だが米国のように、複数の歯車を噛み合わせなければならない。
米国でFASTがウケた理由の一つと違い、そもそも日本での主力はアンテナ経由の直接受信であり、テレビ放送を見る手段がなくなったわけではない。
インフラの都合でテレビが見られなくなったわけではないのだ。
まずここで歯車が一つ欠落する。
テレビ離れについては様々な論が存在するが、米国とのテレビ放送の大きな違いは、メインの地上波放送が、NHK教育を除いてすべて総合チャンネルであるということが大きい。
つまり1つのチャンネルが子供番組からお笑い、ニュース、歌番組、ドラマなど様々なコンテンツを、時系列に沿って放送している。
昭和時代のように、みんながみんな同じ時間に働いて同じ時間に家に帰り、風呂入ってメシ食ってる時代は、こうした総合テレビの時間編成がぴったりハマった。
だが現代は様々なタイムラインで生きている人が大勢おり、標準的な時間編成にはまらない。
「テレビは嫌いじゃないが見るべきものがない」と考える人が多いのは、自分のタイムラインとテレビ編成がズレているからだろう。
見逃し配信のTVerがウケているのも、そのあたりに理由がある。
ここで、2つ目の歯車が欠落する。
もう一つの課題は、テレビ局の権利の持ち方が、米国とは違うということである。
米国のFASTでは、コンテンツは新たに作る必要がなかったというところも大きなポイントだった。
一方日本の放送局は、自分の都合だけでネットに出せる番組をほとんど持っていない。
番組をネットに流すようになって以降、新たに作る番組では権利関係はかなり整理されたが、それでも放映権はテレビ局と制作会社の折半といった形になっている。
古い番組ほど権利許諾の取りようがなくなって、塩漬け状態だ。
テレビ局の独断で配信に出せるのは、ニュース番組ぐらいだろう。
ここで3つ目の歯車が欠落する。
実は日本でも昨年8月にFAST方式のサービスが始まっている。
「FASTch」というのがそれだ。
ただ現状はテレビ番組の再送信ではなく、日本のコンテンツはYouTubeの再送信がかなり多い印象だ。
一方時代劇や韓流チャンネルはテレビコンテンツになっており、これは放送系のチャンネルがそのまま乗り入れているのだろう。
ただYouTubeでも見られるコンテンツを、5分ごとにCMを見させられて視聴するのは割に合わないと感じる人もいるのではないだろうか。
「広告が美味しい」というたった1つの歯車で回そうとしているように感じられる。
日本でも米国のようにFASTが流行ると見ている業界人もいるようだが、米国で普及した事情を見ると、日本では新しい視聴体験として、視聴者に対する別の仕掛けが必要になる。
流行らすには、もっと多くの歯車を見つけなければならない。
参照元:Yahoo!ニュース