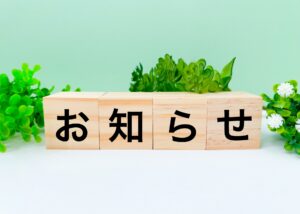そっくり「ニセ日本製」はびこる海外ECサイト 国内メーカー、模倣品対処もいたちごっこ

国内メーカーの模倣品が海外の電子商取引(EC)サイトに出回る事例が後を絶たない。
昨年9月、中東レバノンの爆破事件で使われた大阪の通信機器メーカー製トランシーバーの模倣品は、アジアなどのECサイトで4千件以上の出品が確認された。
模倣品には安全性に問題があるケースも多いが、知的財産に関する法規制は海外まで及ばず、メーカー側の対処の遅れが莫大な損失につながる恐れがある。
昨年9月、レバノンで親イラン民兵組織ヒズボラ戦闘員の通信機器が相次ぎ爆発した事件を報じた英BBCのウェブ記事。
大阪市の通信機器メーカー「アイコム」のチーフメディア広報、松田和也さん(47)は、現場に残されたトランシーバーの写真に写り込んだ自社ロゴ「ICOM」を目にし、手が震えた。
同社ではすぐに対策会議を設置。
爆発した実物は確認できなかったが、海外で人気だった機種と特定できた。
この機種は10年前に製造、販売を終了したことなどから「模倣品」と断定した一方、東南アジアを中心に複数のECサイト上で模倣品の流通を確認した。
今年6月末までに4500件超の出品を停止させたが、多くは正規品と見分けがつかないという。
継続的にECサイトなどを監視する仕組みも構築し、模倣品を見つければECサイト側に出品停止を求めている。
松田さんは「しばらくすると再び出品され、いたちごっこの状態。業務負担増は避けられない」と話す。
任天堂のゲーム機「スイッチ」のコントローラーに化粧品、自転車の部品…。
海外に流通する国内メーカーの模倣品は多岐にわたる。
高性能シャワーヘッド「ミラブル」で知られるサイエンス(大阪市)も模倣品に悩むメーカーの一つだ。
同社が模倣品を最初に確認したのは約3年半前。
ECサイトでミラブルを購入した国内の消費者から「水が出ない」などの問い合わせが相次いだためだ。
模倣品も見た目は瓜二つだが、明らかに異なる材質の部品が使用されていたという。
その後、海外のECサイトでも模倣品が見つかり、その都度サイト側に出品停止を要請している。
日本の税関からは、輸入された模倣品を水際で差し止めたとの連絡も4千件ほど寄せられた。
大阪・関西万博で「ミライ人間洗濯機」を展示し、さらなる海外進出も模索する同社の担当者は「模倣品の存在は今後の支障になりかねない」と困惑する。
模倣品の流通は世界的な問題だ。
経済協力開発機構(OECD)が2021年にまとめた報告書によると、世界の模倣品被害は米国が全体の39%を占め、日本も7位。
逆に供給元は中国54%、香港22%、トルコ12%と続く。
また、財務省の調査によると、日本の税関が昨年、輸入を差し止めた知的財産権侵害品は過去最多の3万3019件だったが、送り元は中国が2万6604件と全体の実に8割にのぼる。
特許庁海外展開支援室の担当者は、インバウンド(訪日外国人客)の増加などを背景に日本製への注目が高まり、大手だけでなく中小メーカーの模倣品が海外ECサイトで出回るケースもあると指摘。
現地で先に商標登録されると権利保護が届かず海外展開の障害になるとし、「中小企業も模倣品対策の必要性を自覚してほしい」と訴えた。
日本企業の模倣品被害は、2021年のOECD報告書に基づく推計によれば、年294億ドル(当時約3兆1千億円)にのぼる。
隣の韓国もポップカルチャーの世界的人気などを受け、被害は年97億ドル(同約1兆円)と多額だが、国を挙げての対策が進む。
日本側も今後、一歩進んだ取り組みが求められる。
OECDの報告書に基づく日本貿易振興機構(ジェトロ)のまとめによると、20~21年における韓国の模倣品被害の51%は電子製品だが、衣類が20%、化粧品も15%にのぼる。
「韓流」と呼ばれる大衆文化が拡大する中、化粧品や衣類など「K(韓国)ブランド」の模倣品も横行しているとみられる。
ジェトロによると、韓国特許庁は商標権侵害の取り締まりに特化した特別司法警察を設置。114カ国のECサイトで模倣品の流通状況を調べ、23年に約16万件、24年は約19万件の流通を遮断した。
AI(人工知能)を活用した対策も進む。
さらに海外での流通を阻止するため、官民連携の「Kブランド保護官民協議会」を発足。
中国や東南アジアなど8カ国10カ所に設置する知識財産センターと連携し、訴訟対応などを支援する仕組みも整備している。
日本製品の模倣品は、かつて海外に流通してもアジアの一部地域の露店などだけで見られ、メーカー側も損失を軽微とみていた。
ただ、ECサイトの普及で世界規模で取引されるようになり、状況は一変している。
問題を加速させる最大のポイントは、消費者が正規品と模倣品を見分けにくい点だ。
サイトでは正規品と模倣品が区別なく表示され、写真や値段など限られた情報から真偽を見抜くのは困難だ。
ECサイト側で独自に悪質な出品者を排除することが望ましいが、運営側も真偽を判別できず、メーカー側に一任するしかないのが現状だ。
しかし、中小規模のメーカーには国内外のECサイトで模倣品を監視する体制を整える余裕がない。
サイト運営側に指摘された模倣品の速やかな出品停止や、悪質業者の利用を禁じる仕組みの導入を義務化するなど国際的な環境整備が急務だ。
欧州や韓国では、模倣品の存在が深刻な問題として議論が進んでいる。
日本も国内メーカーの権利を保護するため、より積極的な議論が必要だ。
参照元:Yahoo!ニュース