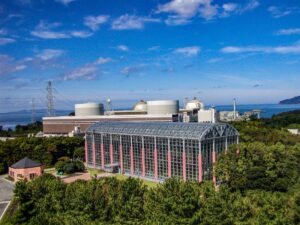歯科医院は「斜陽産業」なのか? 倒産・休廃業が過去最多ペースの背景にある“本当の理由”

「帝国データバンク」の「歯科医院」の倒産・休廃業解散動向によると、2024年に発生した歯科医院の倒産(負債1000万円以上、法的整理)は前年比倍増の25件、休廃業・解散(廃業)が101件発生し、2024年10月までに計126件が市場から退出したという。
「2022年は92件、2023年は104件が退出しています。年々、歯科医院の倒産は増えている。歯科医院は曲がり角を迎えています」
そう語るのは、歯科業界専門のコンサルタント事業を手掛ける髙橋翔太氏。
香川県高松市にある「しん治歯科医院」を、開業した父・髙橋伸治理事長とともに、年商8.3億円にまで成長させた実績を持つ。
単院の歯科医院の平均年商がおよそ4700万円(2023年厚生労働省の医療経済実態調査)という数字を鑑みれば、同院の成長は突出していると言えるだろう。
「しん治歯科医院」が躍進した主な要因は、現在の歯科医院を反面教師にしているところが大きいのだが、まず順を追って、なぜ過去最多のペースで歯科医院が市場から撤退しているのか紐解いていく。
「子どもに顕著ですが、虫歯になる人が減っています。フッ化物配合歯磨剤(むし歯予防効果のあるフッ化物が配合された歯磨き粉)などが普及したことや、親世代の健康への意識向上などで、口腔内環境が向上しました。そのため、治療を求めて来院する人が減少傾向にあります」(髙橋氏、以下同)
次に、経営者の高齢化が挙げられるという。
「経営者の平均年齢が60歳を超えるなど高齢化が進んでいます。2024年の「休廃業・解散」となった歯科医院の代表者年齢は、69.3歳と70歳に迫っているほどです。また、歯科医院は、家族経営のケースが多く、後継者不足問題に悩まされるところも少なくない」
過去最多のペースで淘汰が進んでいる――ということは、斜陽の業界として受け取られかねない。
結果、歯科衛生士を含め、人材を確保できずに廃業する歯科医院も多いと髙橋氏は話す。
さらには、昨今の円安状況によって、虫歯治療で使う銀やパラジウムといった合金など、材料費の高騰も経営を圧迫している一因だといい、複合的な理由が重なることで、歯科医院は瀬戸際に立たされている。
だが、こうした理由は、「あくまで表面的なもの」と髙橋氏は語る。
「そもそも歯科医院の数が多すぎるんですね。2024年時点で、全国にコンビニは約5万5000店あります。一方、歯科医院は6万6000〜6万8000軒ある。歯科医院はコンビニより多い。そうした状況下で、治療する人が減っているわけですから、供給過剰になることは明白でした。つまり、治療とは異なるビジネスモデルを作らなければ、今後生き残ることは難しくなっていきます」
事実、「しん治歯科医院」は、治療に加え、予防に重点を置くことで成長を遂げた背景を持つ。
同院は、口の健康を求めて予防をしに来る人を増やすために、歯科治療のアシスタント的な存在になりがちな歯科衛生士を主役にするビジネスモデルを作り出した。
歯科衛生士は、「歯科予防処置」「保健指導」「診療補助」「口腔機能訓練」を行う、言わば予防歯科、健康づくりのプロフェッショナルだ。
「歯科衛生士は、国家資格者であるにもかかわらず、給料が安く、休みも取れないうえに、歯科医師のアシスタントとしての仕事や雑務ばかりすることが珍しくない。『本当は歯周治療や予防歯科の仕事がしたい』と考えている歯科衛生士は多く、彼ら彼女らのやりがいを創出することができれば、予防の重要性を患者さんが理解し、リピートを生む好循環になると考えた」
治療中心の歯科医療は、「治療が終わればおしまい」である。
だが、予防中心の歯科医療は、長期的な関係性を築くストックビジネスになりえる。
2020年には、歯科疾患の重症化を予防するための保険適用の範囲が広がったこともあり、歯の予防がリーズナブルにできるようになったことも後押しした。
実に、しん治歯科医院の年商8.3億円のうち、予防2億円、訪問歯科3億円――収益の半分以上を予防と訪問で計上する。
同医院の予防における患者リピート率は99.2%を誇る。
「お口が健康であり続ければ、健康寿命を延ばすことができます。歯科医院がコンビニの数より多いということは、やり方次第では地域のインフラになれます。もっと健康になりたいという思いを叶える、人々の健康を支えるハブになれる可能性を秘めているということです」
しかし、多くの歯科医院があぐらをかいたままだと語気を強める。
「治療に重点を置くと、単価の高い治療は何かという発想になりがちです。生き残るために高額な治療を正当化しようとします。本当にすべての人がそのクオリティを望んでいるのでしょうか。また、私はコンサルをする中で、多くの歯科医院経営者と顔を合わせますが、『早く辞めたい』と漏らす院長先生が本当に多い(苦笑)。前提として大変な仕事であることは、実家が歯科医院なので十分に承知しておりますが、それでも自分ファーストかつ、根本的なモチベーションの低さが、スタッフ離反、業績悪化や廃業につながっている感は否めません。歯科医師である以上に、経営者である院長先生にはいつまでも夢を語っていてほしい」
現在、髙橋氏は予防に重点を置くビジネスモデル“デンタルフィットネス”を、全国の歯科医院に普及している。
同氏がメスを入れた歯科医院190軒は、すべて業績が改善しているという。
「歯科医院は、家業型ビジネスであるため、常に成長し続けるという意識が希薄です。端的に言えば、企業的感覚で経営するという感覚が乏しい。そのため、歯科衛生士という経営資産・人材を上手に機能させるといった発想にならないんですね。裏を返せば、少しの覚悟を持って改革する気持ちがあれば、今ある環境に追加投資せずに経営を立て直せる歯科医院は多いんです」
こうした流れを受け、今後は予防をうたう歯科医院が増えることが予想される。
しかし、「ユーザーファーストではない歯科医院は、何をしても経営は厳しくなる」と髙橋氏は断言する。
それを示す一例として、こんなアドバイスをおくる。
「予防は、基本的には3カ月に1度くらいのペースで行えば十分です。その際、私たちは、しっかり1時間をかけて患者さんのお口の状態をチェックします。しかし、中には30分程度で終える歯科医院もあります。はっきり言って、これでは十分な予防はできません。保険が適用されるということは、やらなければいけないことが決まっているということ。そのプロセスは、とてもじゃないですが30分では終わりません。時間一つを取っても、患者さんのことを考えているか、いないかがわかります」
髙橋氏は、「ユニクロが普段着を『LifeWear』と再定義したように、歯科業界も予防歯科を『健康づくりのインフラ』と再定義し、真剣に取り組んでいかなければいけない」と語る。
それができる歯科医院と、旧態依然とした歯科医院の二極化が進んでいくと髙橋氏は考えている。
「これからの歯科医院は、『健康づくりとは何か』という根本的な問いに向きあっていくべきです。健康であるのは患者さんだけでなく、歯科衛生士を含めたスタッフ全員、そして経営者である院長先生も健康でいつづけなくてはなりません。最先端の治療技術への傾向も大変素晴らしいことですが、一方で過去最多で倒産しているのは、そのツケとも言えます。顧客不在の姿勢の表れです。目の前の患者さん一人ひとりの健康作りをサポートするという“当たり前”を提供できていない歯科医院が多い。今こそ、歯科医院は本来の役割を思い出さなければいけません」
参照元:Yahoo!ニュース