2025参院選で氾濫するデマ 日本では「表現の自由」から規制に慎重 海外での対策は?
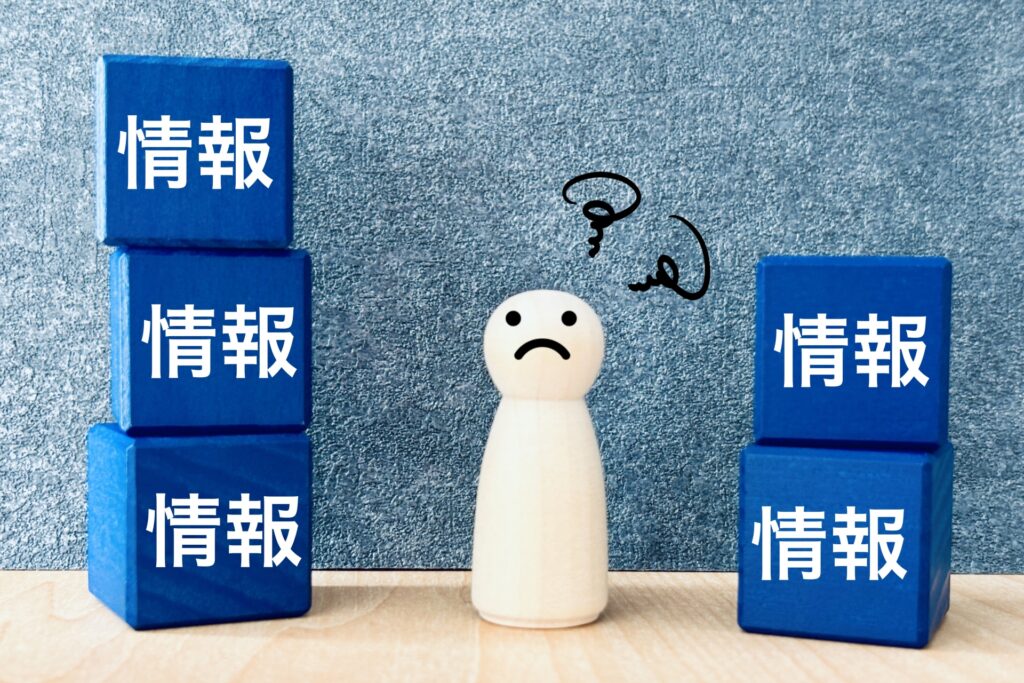
参議院選挙ではかつてなく外国人が焦点になり、それに比例してネット上のデマも増える一方、外国の選挙干渉とみられる事案も報告されている。
事実でないことを意図的に伝える「偽情報」の氾濫は社会の分断を促すだけでなく、安全保障リスクでもある。
つまり偽情報には二重の懸念があるが、この点で日本はぜい弱だ。
読売新聞が昨年日米韓で行った調査では、日本のユーザーはネット情報の元情報を確認しない傾向が最も強かった。
ところが、その規制は表現の自由にもかかわるため日本政府は慎重だ。
これに対して海外には、より踏み込んだ対策も目立つ。
総務省は表現の自由を重視し、政府介入は極めて慎重であるべきとの立場から、プラットフォーム事業者による悪質投稿削除やファクトチェックといった自主的取組を重視している。
これに対して、例えばEU(欧州連合)はプラットフォーム事業者の実施規範に基づいて、偽情報を発信するアカウントの広告収入規制や、事業者の取組に関する定期的評価などの改革を進めてきた。
これはいわば事業者の自主的取組を公的機関が強く後押しするもので、豪州も同様の実施規範を採用している。
ただし、イーロン・マスク氏に買収されたTwitterが2023年、EU実施規範を離脱したと報じられたように、自主的取組であることの限界もある。
一方、台湾ではむしろ第三者機関による偽情報の洗い出しに力点がある。
中国との関係を背景に偽情報が氾濫してきた台湾では、常時ネット上でファクトチェックを行う非営利団体が数多くある。
メディア報道やSNS投稿を分析し、フェイクと確認されれば公的機関や関連事業者に警告していて、AIなど先端技術の導入がこれを支えている。
このように手法に違いはあるが、偽情報は選挙だけでなく災害でも氾濫しやすいため、日本も今後より本格的対策が求められるだろう。
参照元:Yahoo!ニュース

