「早い者勝ち」の宇宙ビジネス急拡大 先行する米中を追走へ、政府目標は国内市場を2倍に
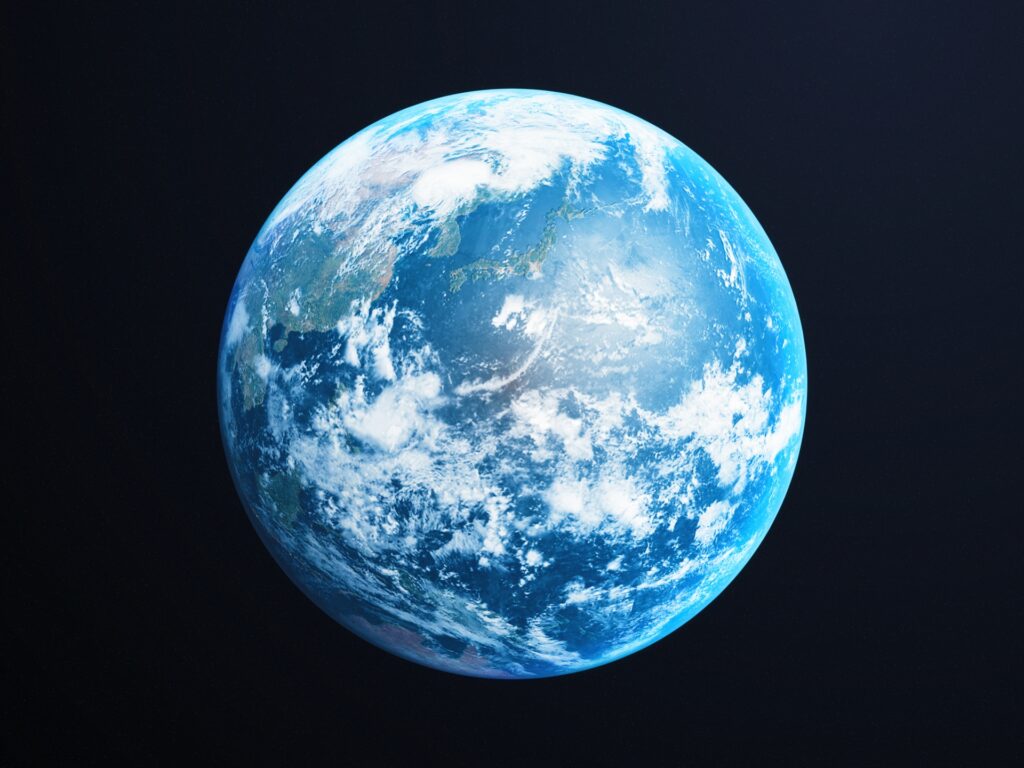
企業が宇宙関連事業を強化する動きが目立っている。
自動車や銀行といった異業種に加え、新興企業の参入も相次ぐ。
ただ、宇宙産業は世界で競争が激化し、米国や中国が先行しているのが現状で、官民一体となった育成策が求められる。
ホンダは6月、機体を繰り返し使える「再使用型」の小型ロケットの離着陸実験に、国内の民間企業で初めて成功した。
自動運転などで培った技術を活用した。
研究開発を担った子会社・本田技術研究所の大津啓司社長は8日に東京都内で講演し、「宇宙は新たな可能性の場だ」と強調した。
通信や金融の大手なども宇宙事業を強化し、新興企業の参入も増えている。
宇宙振興に取り組む一般社団法人「スペースタイド」の調査では、国内の宇宙関連の新興企業は2025年に109社に上り、3年前から4割近く増加した。
宇宙は安全保障や通信分野などで利活用が広がり、産業の急成長が見込まれている。
世界市場は35年に260兆円を超え、23年比で約3倍に上るとされる。
技術の実用化では米中両国が先行し、内閣府によると、24年のロケットの打ち上げ数は米国の153回、中国の66回に対し、日本は5回にとどまった。
米国では商用利用が多く、実業家イーロン・マスク氏が率いる米スペースXがコストを抑えられる再使用型を活用し、大半を占めた。
日本勢はコストの高さも課題で、三菱重工業は宇宙航空研究開発機構(JAXA)と共同開発する新型主力ロケット「H3」で、打ち上げコストを従来の半分の約50億円まで引き下げることを目指す。
政府は6月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」で、宇宙政策を強化すると明記。
国内市場を30年代前半に、20年の2倍の8兆円に引き上げる目標を掲げる。
宇宙開発は「早い者勝ち」(経済官庁幹部)の様相で、事業化の速度が勝敗を分ける。
スペースタイドの石田真康代表理事は「主要国に限らず、世界中が産業育成に取り組んでいる。日本もより需要を刺激し、人材や技術、投資を獲得することが不可欠だ」と指摘する。
参照元:Yahoo!ニュース

