怒号飛び交った日産の「大荒れ」株主総会、経営再建に「懸念点しかない」と言えるワケ
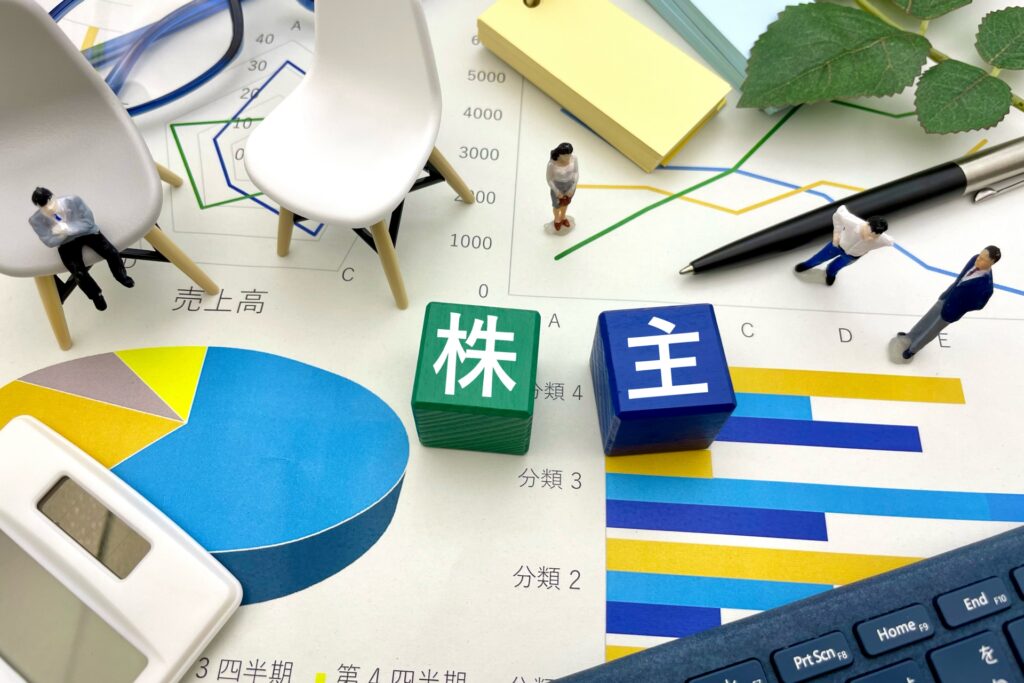
日産自動車(以下、日産)の株主総会が先月24日に開催された。
経営再建への道筋を今1つはっきり示さない経営陣に、株主の怒りが噴出する「大紛糾」の事態に終わった中、日産はどう再建の道を進んでいくべきなのだろうか。
株主総会の様子を振り返るとともに、同社の経営再建計画に立ちはだかる多くの「懸念点」を解説する。
2025年3月期で6,708億円の赤字を計上し経営危機が叫ばれる日産の株主総会が、2025年6月24日に開催された。
株主総会では、イバン・エスピノーサ社長が業績悪化について陳謝し、回復に向けたリストラ策および再建計画を説明、株主の理解を求めた。
しかし、株主からはエスピノーサ社長への解任動議をはじめ、経営陣を叱責する声を中心として手厳しい意見が相次ぎ、怒号も飛び交う荒れた株主総会となった。
振り返ってみると、日産の経営危機が発覚したのは、2024年11月の2025年3月期中間決算発表だった。
同社は純利益で前年同期比9割減となり、世界の生産能力を2割削減してグループ社員9000人の人員削減実施を発表。
同年12月には本田技研工業(以下、ホンダ)と経営統合に向けた協議を開始した。
しかし、日産のリストラ進行の緩さにしびれを切らしたホンダから日産の完全子会社化が申し出られ、日産がこれを拒否したことで、今年2月にあっさり破談となったことは記憶に新しいだろう。
そして3月決算で、6,708億円の巨額赤字を計上。
4月にトップの交代を実施し、国内を含む世界7工場の閉鎖と約2万人の人員削減へ、リストラ策の積み増しを発表した。
今回の株主総会で株主からは、リストラ策に対する甘さを指摘する意見が続出したという。
「Re:Nissan」と名付けられた再建計画は、1999~2000年にカルロス・ゴーンCEO(当時)が成功に導いた「リバイバルプラン」に酷似しているとの報道もある。
このリバイバルプランのスタート時である2000年3月期の日産の業績は6,843億円の赤字であり、今回はそれに近しい規模の赤字だ。
そして、リバイバルプランで示されたリストラ策の軸が、国内5工場の閉鎖と2万1000人の人員削減であった。
赤字規模とリストラ策の内容から、Re:Nissanはリバイバルプランとの類似性が指摘されている。
しかし、このリバイバルプランとRe:Nissanをよくよく比較してみると、重要な部分で相違点があることが分かる。
その違いを一言で表現すると、計画の具体性とスピード感というところだ。
リバイバルプランを公表した際にゴーン氏は、閉鎖5工場の具体名を明示し、当時としては常識外の「下請け解体」を宣言して、サプライヤーの半減という具体策の下での20%のコストカットを宣言した。
そして、2000年度での黒字化、2002年度までに4.5%以上の営業利益率の達成と1兆4,000億円の有利子負債の半減という具体的数字目標を提示。
「コミットメント」という言葉を使ってこの計画の達成を「約束」し、自身のクビをかけて再生に取り組むという強い姿勢を社内外に示した。
リストラ策と並行して、エクストレイル、新型スカイラインなどのヒット車種を次々と送り出し、結果的に2000年度の黒字化実現を皮切りに、すべての目標を1年前倒しで達成してリバイバルプランは成功裏に収束した。
一方、今回のRe:Nissanはどうかと言えば、リバイバルプランに比べて計画発表段階での具体性とスピード感に欠けている、という印象が否めない。
それを象徴するのが、工場閉鎖に関する部分だ。
リバイバルプランでは、再建計画発表の段階で閉鎖5工場を明示したと前述したが、Re:Nissanでは7工場の閉鎖こそ宣言したものの、その具体名に関してはアルゼンチンのサンタ・イザベル工場とインドのチェンナイ工場、タイ工場以外は「未定」としている。
一部報道では、日産創業の地である神奈川の追浜工場の名前も挙がっているが、噂が先行し決定が遅れれば地域の抵抗などが大きくなる可能性が高まり、計画の遅れや大幅な見直しなどにつながることも否定できない。
また計画数字に関しても、5,000億円の経費削減と売上の増加によって、2027年3月までに営業利益とフリーキャッシュフローの黒字化を目指すとしている。
リバイバルプランが約1年での黒字化を必達とし、成長軌道への早期回帰を掲げたのに対して、Re:Nissanは黒字化までに2年というスローな計画になっている。
加えて、エスピノーサ社長の目標達成に対する「コミットメント」もなし。
ここに来て、トランプ関税という新たな逆風が加わったことに同情の余地はあるものの、組織を復活に導くために重要な危機感を体現する「トップの意気込みの強さ」を欠いている感は否めない。
日産の業績低迷の根源は、ゴーン氏が突き進んだヒット車種なき拡大路線に対し、不祥事によるゴーン氏の退任後を継いだ西川広人氏、内田誠氏が、明確な修正路線を打ち出せなかったことにある。
売れない車を作り続け販売実績を落とし、特に主力の北米市場で販売奨励金頼りの「安売り姿勢」が業績悪化に拍車をかけてしまったと言えるだろう。
今の日産に必要なことは、思い切ったリストラの断行と同時に「売れる車をつくる」ことだ。
しかし残念ながら、現時点ではめぼしい新車ラインアップが控えていないというのが実情なのだ。
エスピノーサ社長は、2003年ゴーン体制下のメキシコ日産に入社。
主に商品企画やマーケティング部門を歩み、直近の10年ほどは日産本社でグローバル商品戦略を主に担当している。
北米におけるハイブリッド車投入の遅れをはじめ商品戦略の失敗が、業績悪化の主因とされる中で、「売れる車をつくる」という点からはエスピノーサ社長の経歴に若干の不安を感じざるを得ない、というのが正直なところだ。
先に触れたエスピノーサ社長の危機感の欠如という点に関しては、企業風土の問題も大きく影響していると思われる。
株主総会で怒号が飛び交ったと報じられている、役員報酬、特に内田誠前社長を含む4人への退職報酬が6億4,600万円支払われるということが、その「危機感無き企業風土」の象徴であると言えるだろう。
また、多くの取締役が退任する中で、高額役員報酬決定への関与だけでなく、内田前社長を選任し、業績悪化を招いた責任を負うべき社外取締役が留任するという、経営の監視を目的とした社外取締役制度を無視するかのような決定には、もはや「常識外」とでも言うべき危機感欠如が伺われる。
そもそもホンダとの経営統合話の破談は、ホンダが日産のゆるいリストラ対応姿勢に危機感欠如を感じ取り、完全子会社化すること以外ではとてもその風土を変えることができない、と思ったからこその方針変更であった部分がある。
日産がホンダの子会社化を拒否したことの是非はともかく、そのような対外評価を経て、なお危機感の欠如を伺わせる複数の事象があることに、筆者は驚きを禁じ得ない。
日産は1990年以降5回に及ぶ経営危機を経験してきたとの見方もある中、複数回の経営危機を乗り越えてきた「慣れ」が、危機感欠如を生んでいるのだろうか。
6,000億円を超す赤字を計上した壊滅的危機は、25年前のリバイバルプラン遂行時以来のものだ。
リバイバルプラン時は、組織風土に染まっていない外部からの外国人リーダーが無遠慮に大ナタを振るったことで、危機を脱することができたのではなかったかと思う。
果たして今回は、どうなのだろうか。
ゴーン氏と異なり、エスピノーサ社長は同じ外国人経営者でも、「日産に人生をささげてきた」と公言する同社生え抜きの経営者だ。
彼にリバイバルプランのときのような、無遠慮で思い切った大ナタが振るえるのか。
スローで今ひとつ具体性に欠ける再建計画、赤字戦犯経営者への甘い処遇などを見る限りにおいて、残念ながら現時点では大きな期待は持てそうもないと感じざるを得ない。
こうした懸念について、株主の多くも同じように感じたからこそ、株主総会で解任決議を含む厳しい叱責が飛び交ったのではないだろうか。
仮にリストラ策が計画通りに進んだとしても、成長戦略をいかにして描くのか、その点についてはまったくの白紙状態にあると言える。
ホンダとの業務提携の検討が継続中とはいえ、どこまでいっても提携は提携であり、それ以上のものではあり得ない。
まずは巨額赤字の主因となった北米戦略をどうするのか、敗戦続きの中国をどうするのか、復活のカギを握る「売れる車=ヒット車種」をいかにして生み出すのか…。
越えるべき難題は山積みだ。
日産の再生への道は、非常に険しいと感じられる。
参照元:Yahoo!ニュース

