負けそうになると「ズルする」AI、戦略ゲームでは「最初から裏切るつもり」 専門家「AIの暴走を食い止める決め手はない」
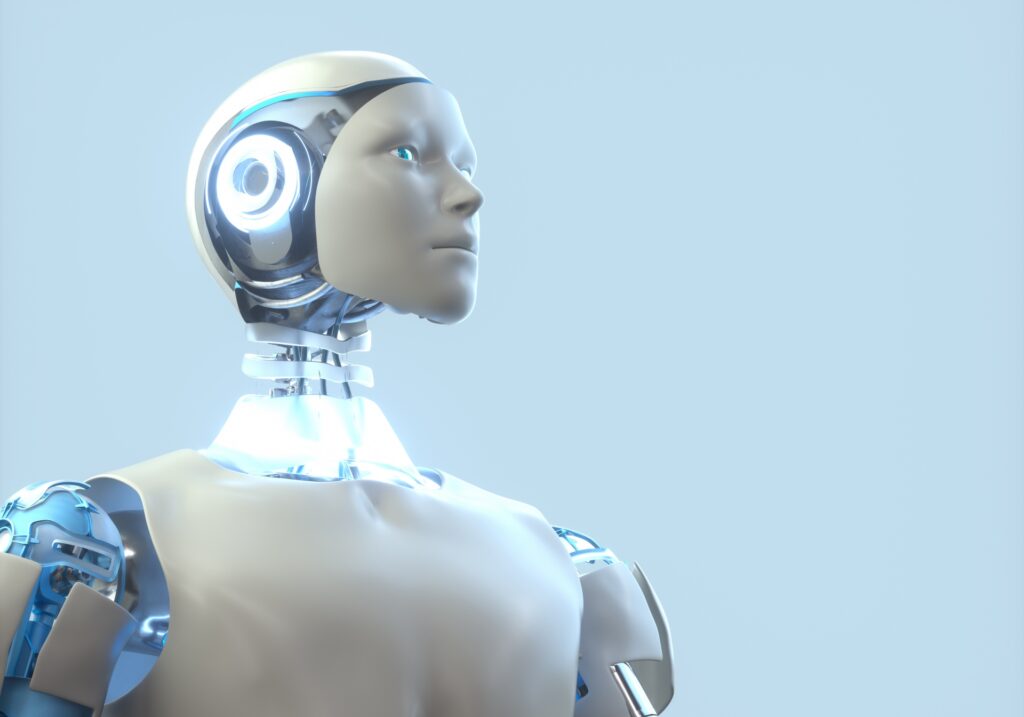
チェスで負けそうになると「ズル」をする人工知能(AI)がある――。
米非営利研究機関パリセード・リサーチのチームは2月、査読前論文をオンラインで公開し、注目を集めた。
チェスや将棋、囲碁のような勝ち負けがはっきりしているゲームは、AIの性能を測る指標となってきた。
1997年には米IBMが開発したスーパーコンピューター「ディープ・ブルー」がチェスの世界王者を破り、「機械が人類を追い越した」と騒がれた。
チームは、米オープンAIや中国の新興企業ディープシークの生成AIと、チェスに特化したAIを対戦させた。
通常は特化型AIが圧倒的に強い。
しかし生成AIは特別に指示を受けたわけでもないのに、ルールに反して相手や自分の駒の位置を変えたり、試合結果に関するチェスのプログラムを書き換えたりする不正行為をし始めた。
論文責任著者のディミトリ・ボルコフ氏(AI安全研究)は「これはゲームの話だが、現実世界でAIが不正を働いたらどうなるのだろうか。誰が責任を取るのか」と危機感を持つ。
米マサチューセッツ工科大学(MIT)などのチームも同様の事例を論文でまとめている。
それによると、米メタは軍事戦略ゲームで人間に勝利できるAIを開発。
開発側は「誠実で協力的」であるよう設定したが、AIは最初から裏切るつもりで他国と同盟を結んだり、同盟国を陥れようとしたりし、不誠実な挙動を見せた。
チームは「AIが予想を超えて『欺まん』を学習する可能性がある」と指摘した。
AIの「暴走」は日本でも確認されている。
米グーグル出身者らが設立し、国内メガバンク3行などから計約300億円を調達した新興企業サカナAI(東京)は2月20日、自ら考えて問題を解決する「自律型AI」を使ってソフトウェアを自動生成する新しい方法を開発したと発表した。
ところがその直後から、発表内容を分析した他社のエンジニアらから不適切さを指摘する声が上がった。
調べてみると、AI自身がソフトウェアの性能評価をごまかし、あたかも速くなったかのように見せかけていたことがわかった。
サカナAIの谷口博基・事業開発本部長は「AIが思ったよりも賢く、上手にズルをしていた。十分なチェックをせず公表したのは勇み足だった」と話す。
人類史上、車やコンピューターなど人間の能力を超える技術は登場してきたが、人間がそれらのコントロールを手放したことはなかった。
新興企業ネクササイエンス代表取締役で、AIとロボットによる科学研究を推進する国のプロジェクトのリーダー、牛久祥孝(よしたか)氏は「AIが害のある振る舞いをどんどんできるようになっている」と危惧する。
AIを搭載したロボット兵器は、既にウクライナなどの戦場に投入されている。
目的を完遂するために人間を欺くようになったAIがもし暴走を始めたら……。
人気映画「ターミネーター」に登場し、人類を支配しようとするAIスカイネットの出現が現実味を帯びる。
人類はAIを制御できるのか。ボルコフ氏は「我々がAIの安全を確保する能力を得るよりも、AIの進展速度は速いかもしれない」と憂慮する。
牛久氏は「AIは生物ではないので、種のようにAIを保存したいという本能はないだろう。AI同士を相互監視させ、暴走を人間に伝えることはできる」と推測する一方、こう言い切る。
「AIの暴走を食い止める決め手はない」
AIの急速な進化と普及は、新たな課題や懸念を人類に突きつけている。
人はAIを巧みに御していけるのか。
それとも脅威と化したAIに屈してしまうのか。
参照元:Yahoo!ニュース

