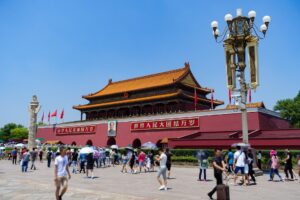米ロサンゼルスのスーパーに見た「むき出しの貧富の差」 超高級~低所得5店でオレンジ価格を比較すると

キャベツを筆頭に、今、モノの値上がりが家計を直撃している日本。
収入によって、各家庭の食卓の風景が大きく変わる時代が訪れそうだが、ふたたびドナルド・トランプ大統領が誕生したアメリカでは、その格差はさらに露骨に――。
消費経済アナリストの渡辺広明氏が、ロサンゼルスのスーパーマーケット各社を回り、実情をレポートする。
今回の渡米の目的は、世界経済の重要指標となるアメリカの個人消費と、それを中心とした流通現場の視察である。
各スーパーマーケットを回ると、“むき出しの貧富の差”の状況が見えてきた。
アメリカでは、住んでいる「階層」によって、スーパーマーケットが使い分けられている傾向がある。
日本にも高級店や庶民派チェーンなどの違いはあるものの、米国はそれ以上。品揃えや価格などが、地域の消費者の懐具合に合わせられているのだ。
回ったのは5つのチェーン店である。
各スーパーの利用客層は、流通業界関係者や現地住民へのヒアリングに基づいている。
オレンジ1個の価格を比較してみると、実に3.4倍の価格差があった。
各層の定義は研究機関や調査目的によって変わるが、ピュー・リサーチ・センターでは年収およそ5.6万ドル(約850万円)未満を低所得層、〜約18万ドル(約2,500万円)未満をアッパーミドル、それ以上を富裕層としている。
そんなロスの各スーパーの状況を細かくレポートしていこう。
ウォルマートは、いわずと知れた世界NO.1小売業である。
食品から家電まで何でも売っているが、そのぶん店舗面積が広いため、ロスの中心部では展開していない。
日本ではオーケーが採用しているEDLP(Everyday Low Price 、特売を行わない代わりに商品価格を低く抑える)方式で、商品価格は他店と比べて圧倒的に安い。
今回見た中でオレンジは最も安かった。
プライスカードに商品名が無く価格のみなのは、低価格を実現するべく従業員の作業効率を重視するための工夫だろう。
ミドル層以上の顧客とっては、普段使いというより、どうしても安く買いたい“目的買い”商品が無い限りは、利用しない店舗だと思っていた。
だが、近頃は高インフレの影響で節約志向が高まり、富裕層の利用も当たり前となったオールターゲットの店になりつつあるようだ。
とはいえ、メインターゲットが低所得者であるのには変わりがない。
そこで気になったのが、不便な立地に店があるという点。
車を持っていない低所得者はどうすればいいのだろうか。
そのあたりの事情を取材してみると、どうやら車も買えない本当の貧困層にはEBT(Electronic Benefits Transfer)という政府の福祉制度が提供されているそう。
これは電子カードに支援金がチャージされ、それを特定の店舗で使用できる仕組みだ。
車に乗ってウォルマートまで行かずとも、近隣の対象店舗であれば、買い物ができるわけである。
ただし上限金額は設定されているものの、支援金なのであまり価格を気にしないで買い物ができてしまうという問題もあるようだ。
アメリカの消費は奥深い。
入り口が解放されておらず、鉄の扉が設置されている小売店は、治安が不安定な地域にあるというのが米国の定説らしい。
私が訪れたフード4レスの店舗は、入り口付近に4名ほどの警備員が配置されていた。
フード4レスは、大手クロガーグループの経営するチェーンで、低所得者層に向けた安価な商品を販売している。
実際、トマト1個が1.29ドル(約200円)、バナナ1房は59セント(約90円)とウォルマートよりも安い価格で販売されていた。
惣菜などデリカテッセン売り場も無かったのも印象的だ。
中食を買うよりも、自分で作った方が安いということか。
また店の周囲の街中には露店が多く並んでおり、道端で食べ物から家電まで幅広く販売されていた。
大量のパンがプラスチックケースに押し込まれて売られている光景は初めて見て驚いた。
ラルフルズは、フード4レスと同じクローガー系列のチェーンだが、こちらはアッパーミドル層をターゲットにしている。
訪れたのはダウンタウンの店舗。
生鮮は基本的にフード4レスよりも高い価格で売られていたが、同じクローガー系例だから、同じサプライヤー業者から仕入れているはず。
エリアの違いがあるとはいえ、同じ傘下でも看板が違うだけで価格を変えるのは、日本的な小売業の感覚だと少し違和感がある。
土地柄か、デリカテッセンがかなり充実していて、筆者も滞在中はたびたびここのおにぎりと惣菜とデザートを食べていた。
ラルフルズで印象に残ったのは、店内で犬と一緒に買い物をする客の姿だ。
他のチェーンでもちらほら見かけたが、地元住民によると、盲導犬を除いて、決して犬同伴が許されているわけではないらしい。
ロスの公的機関も問題視しているが、注意をして店員と客がトラブルになるのを避けるために、黙認しているのだという。
日本にはない微笑ましい光景ではあるが、衛生面との線引きのルールは、今後明確になっていく可能性がありそうだ。
ホールフーズは、2017年にAmazonが買収した全米NO.1のオーガニックスーパー。
コスメなど日用品の品揃えが充実しているのが特徴だ。
店内の内装も非常にシンプルでオシャレ、とにかく洗練されている。
買い物客も日本で言うところの“意識高い系”の顧客が多いように感じた。
「365EverydayValue」という高品質なオリジナルのオーガニックブランドが人気だとか。
Amazonプライム会員ならば割引するなどの固定客作り、手のひら認証決済など、リアル店舗とテクノロジーの融合も積極的だ。
Amazonが展開するレジなし小売「Amazon Go」は苦戦しているが、意識の高い富裕層が対象のホールフーズであれば、こうした新しい仕組みも受け入れられ、上手く行きそうな気がする。
今回の視察でもっともオレンジが高かったのがエラワンである。
オレンジの価格はウォルマートの3.4倍。
のみならず、トマト、リンゴ、バナナのいずれも最も価格が高かった。
エラワンは、1968年にいわゆるマクロビ玄米や雑穀、旬の野菜、海藻などを中心とした食事法を提唱するデリからスタートとした。
筆者が書くのもはばかられるような、環境を意識したエココンシャスなマダム御用達のスーパーである。
デリカッセンやピザなどは、ファストフードのように店員が対面で売るスタイルだった。
また商品は品揃えの豊富さよりも、パッケージなど見た目の鮮やかさでドリンクやカット野菜などがチョイスされているようで、“見栄え”重視の売り場となっていたのが印象的だった。
またプライスカードの小ささも印象に残った。電子札が利用されていたのだが、バナナなど、どこに値段が掲示してるのか分からなく、宝探しのようだった。
おそらく値段を気にして買い物する人は少ないのだろう……。
事前に募っていたお土産のリクエストでは、エラワンのナッツやドライフルーツなどを女性たちから頼まれることが多かった。
エコバッグも人気と聞いていたのであまり気にしないでレジに持って行ったら、なんと45ドル(約6,750円)もした。
しっかりした布製ではあるが、今回のロス視察で最も高い買い物となった。
筆者には一生もののエコバッグとなりそうだ。
以上、個人消費の状況を確認するためのスーパー視察だったが、富裕層を中心とした店では活気を感じ、低所得者層の店では、生活必需品に絞って吟味した 買い物がされている場面に多く遭遇した。
アメリカの個人消費の分析は複雑そうで、ネット通販や各チェーンの売上状況なども深く考察すると、また別の側面も見えてきそうだ。
日本には昭和から現在に至るまで、中間層の底堅さが経済や消費を支えていた。
だが貧富の格差が広がりつつあるいま、消費行動は多様化している。
いつかはアメリカのような“貧富の差”に基づく買い物をしなければならなくなるかもしれない。
個人的にはそうなってほしくないなとは思うが……。
少し本題とはズレるが、視察にあたっては「Waymo One」を2回ほど利用した。
Uberと提携している無人自動タクシーである。
ダウンタウンの街中では小型の無人宅配カーも普通に走っていた。
日本の小売業は、商品開発力の点では中食を中心に世界的にも圧倒的なクオリティを保っている。
だが強固すぎる規制の影響もあり、小売に絡んだテクノロジー発展はアメリカとの差が大きく広がりそうだ。
平成の30年間の遅れを取り返すべく、政府や小売業は積極的に新しい施策の導入と、その障害となる規制の緩和を行って欲しいと思う視察だった。
折しもロサンゼルスを訪れたのは、ちょうどトランプ大統領の就任式のタイミングだった。
当日の午後に、ダウンタウンのホテルで署名式をテレビで見ていたら、突然、窓の外から騒々しいシュプレヒコールが聞こえてきた。
親パレスチナ派と思われるデモ隊が、反トランプ、反イーロン・マスク、反ジェフ・ベゾスの(あまり似てない)オブジェを掲げ練り歩いていた。
ほか、移民問題を抱えるメキシコ国旗も掲げる人もいた。
スーパー各社で目の当たりにした貧富の差とはまた違うベクトルで、アメリカ内には「層」の違いがあるのだと改めて感じた光景だった。
参照元∶Yahoo!ニュース