殺人を犯しても生き続けられる 無期懲役刑 「本当はこの手で殺してやりたい」苦しみ続ける遺族
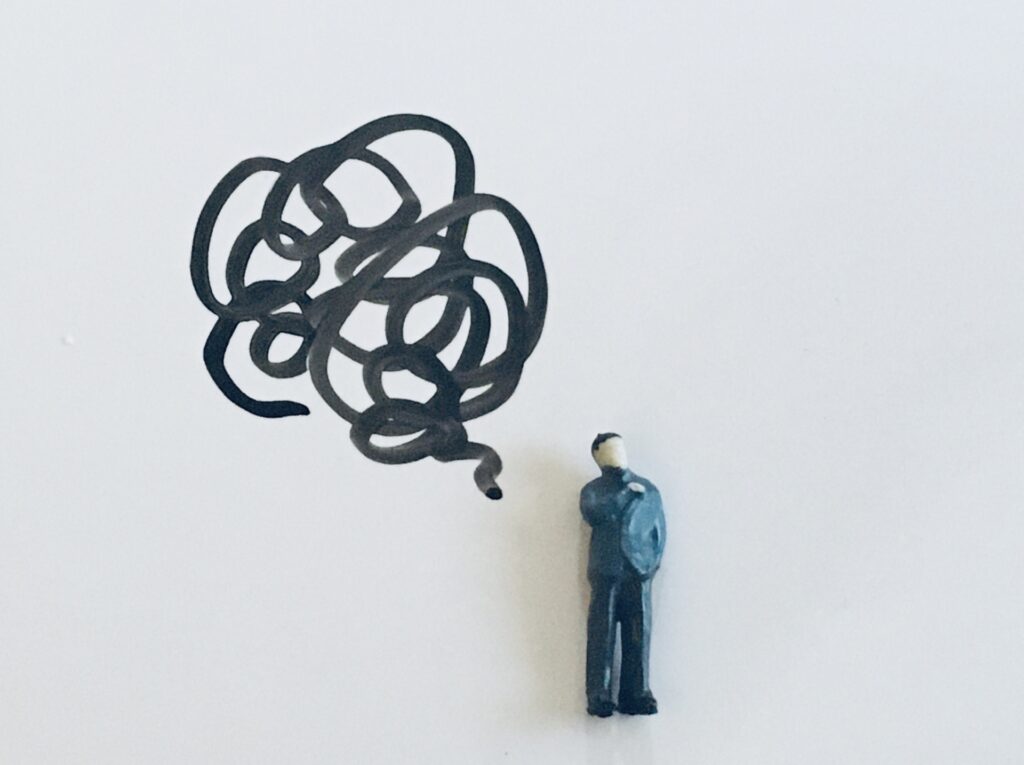
日本の刑法で定められている最も重い刑罰は「死刑」、次にくるのが期限の定めがない「無期懲役刑」だ。
殺人などの凶悪事件ではこれらの判決が下されることが珍しくないが、両者の間には生と死という果てしない深さの溝が存在する。
人を殺めながらも生き続けられる加害者と、当然に来ると信じていた明日を奪われた被害者。
判決が確定した後も、残された家族はその狭間で苦しみ続ける。
「この手で殺してやりたい」。
妻子3人を殺された男性はやり場のない怒りを力のない声で吐露した。
「生きる希望がない」妻と2人の娘を殺害された加藤裕希さん「仕事を終えて帰宅をすると、家族の中で生きているのは私1人だけでした」
2015年9月に埼玉県熊谷市で発生した「熊谷6人殺害事件」。
妻・美和子さん(当時41歳)、長女・美咲さん(同10歳)、次女・春花さん(同7歳)の3人を一度に奪われた加藤裕希(ゆうき)さん(51)は、警察の対応に問題がなかったかを問う民事裁判でそう述べた。
事件から9年。
時間が解決することは何もない。
生き地獄の中で感情の浮き沈みが続く。
昨年3月からの1年間は休職した。
今も1日1日をなんとか生き延びている状態だ。
「本心を言えば、もう死にたいという気持ちです。でも死ぬのは怖い。事件のことを四六時中考えていると自分の身が持ちません。一方で、事件と距離を置くことに罪悪感みたいなものがあります」
次女・春花さん、妻・美和子さん、長女・美咲さん、3つの遺影には、それぞれ同じ日付が刻まれている。
2階建て住宅のリビングには、ゲーム機や子どもが描いた絵などが置かれ、家族4人が暮らす生活感が残る。
しかし、かつて室内に響きわたっていた声が聞こえることはない。
仏壇に並べられた3つの位牌に刻まれた同じ日付が事件の惨状を物語る。
「私は全部を失って生きる希望がありません」
ことの始まりは2015年9月13日、警察による任意の事情聴取を受けていたペルー国籍のナカダ・ルデナ・バイロン・ジョナタン受刑者(当時30歳)が熊谷警察署から逃げ出したことだった。
翌9月14日、熊谷市内に住む夫婦2人を殺害。
さらに2日後の9月16日、84歳の女性に加えて、加藤さんの妻と娘2人の命を奪った。
裁判員裁判として審理された1審のさいたま地裁は2018年3月、ジョナタン受刑者に死刑を言い渡した。
加藤さんは「当然だと思っていた」が、2審の東京高裁は2019年12月、死刑判決を破棄し無期懲役の判決を下した。
ジョナタン受刑者が事件当時、責任能力が著しく低下した心神耗弱(しんしんこうじゃく)の状態だったというのが主な理由だった。
加藤さんは判決が下された瞬間をいまだに忘れることができない。
「結局は無期懲役にするための理由しかくみ取られておらず、納得できない。裁判官が同じ目にあったら、『あなただったら飲み込めるのか?』と言いたい」
追い打ちをかけたのは、検察が上告を断念したことだった。
「我々の味方だったはずの検察が一方的に上告できないと決めて、本当に失望しました」
裁判員裁判は国民の感覚が司法に反映されることを期待して導入された。
国民から選ばれた裁判員が悩み抜いて選んだ死刑判決が覆されたことで、加藤さんは「本当に人間が嫌いになってしまった」という。
無期懲役囚の多くが獄死している今、無期刑は”終身刑”化していると言われる。
だが、被害者や遺族にとって死刑との間には埋めることのできない差が存在する。
死刑囚は毎日が死と隣り合わせの生活に置かれる一方、無期懲役囚は明日も生きることが許される。
そして、再び社会に戻れる「仮釈放」の可能性が残されている点も大きな違いだ。
「死刑になったとしても救われません。ただ、加害者が今生きていることに比べれば少しは救いになるかもしれません。本当はこの手で殺してやりたい」
言葉は強いものの、加藤さんは力のない声で伏し目がちに語った。
2004年10月5日、面識のない鹿嶋学・無期懲役囚から殺害された北口聡美さん(当時17歳)受刑者の仮釈放は、本人に改善更生の意欲があるかなどを基準にして地方更生保護委員会が決める。
その審理には被害者や遺族の意見を聞き取る手続きもある。
ジョナタン受刑者が将来、仮釈放の審査に入った場合、殺害された家族3人の意思を代弁できるのは加藤さんしかいない。
ただ、無期懲役囚は近年、仮釈放されたとしても刑務所の平均在所期間が30年を超えており、これから数十年先も加藤さんが健康でいられる保証はない。
加藤さんが亡くなれば、遺族の生の声を仮釈放の判断に反映させることもできなくなる。
ジョナタン受刑者の仮釈放について、加藤さんは「考えたこともない。1日も早く死んでくれと思う」と率直な心境を明かした。
「なんで娘がおらんなってお前が生きているのか。生きていること自体、許すことができない」、そう話すのは、広島県廿日市市(はつかいちし)に住む北口忠(ただし)さん(66)。
2004年10月5日、長女の聡美さん(当時高校2年生の17歳)を殺人事件で失った。
北口さんはいつも朝が苦手だった聡美さんを起こして出勤していたが、その日、聡美さんは高校で試験があり早く家を出たため顔を合わせなかった。
病院で再会した娘は眠っているようにみえたが、体を揺り動かしても目を開けることはなかった。
火葬を終え、聡美さんの骨を骨つぼに入れる時、拾い上げた骨の軽さが娘の死を突きつけた。
事件は長い間、未解決だった。
命日を迎えるたびに強まる苦痛と焦り。
そんな年を12回も繰り返していた2018年4月、突如、被疑者逮捕の一報が入った。
のちに無期懲役が確定した鹿嶋学受刑者(事件当時21歳)は、聡美さんを強姦しようと家に侵入し、抵抗されたためナイフで何度も刺して殺害。
姿を見られた聡美さんの祖母も刺し、その場に居合わせた妹にも手をかけようとした。
犯行の直前、寝坊による遅刻で勤務先の会社に行くのが嫌になって逃げ出し、住んでいた山口県から東京方面に向けて原付バイクを走らせていた。
その際に下校中だった聡美さんを偶然見かけて狙ったのだった。
事件後に逃走し、14年近くの間、自首することなく生活していたが、別の暴行事件で取り調べを受けた際にDNA型や指紋が現場に残されたものと一致し、聡美さん殺害への関与が発覚した。
北口さんは極刑を願ったが、現行の法律や判例では無期懲役が限界だった。
「家族を奪われた人間にとって死刑以外はありません。なんで娘がおらんなってお前が生きているのかと。詐欺や傷害事件であれば、加害者に『悔い改めてやり直しなさい』と言えます。でも人の命を奪った人間に『立ち直り』という考えはありません」
かけがえのない家族を殺された人は、加害者が生き続ける無期懲役という刑罰をどう受け止めているのか。
「犯人を世間と隔離するための刑じゃないかと思います。なので、無期懲役刑がまた塀の中から出てくるための刑罰だと考えたら、残された家族は悲しい思いしかしません」
「無期」の懲役刑であるのに刑を受けた人がまた社会に戻ってくるかもしれないという現実に、北口さんら遺族の感情は追いつかない。
「せめて無期懲役刑と死刑のあいだに、終身刑のような刑がほしい」
死刑と無期懲役刑、命を奪った加害者と奪われた被害者。
そのあいだにある”生と死”という深い溝は決して埋めることができない。
17歳で殺害された聡美さんが生きていれば、今年7月で37歳になっている。
参照元∶Yahoo!ニュース

