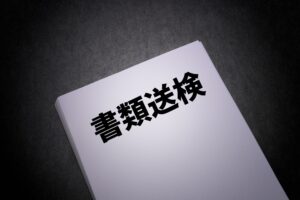「死せる川」にアユ 名古屋の中心部を流れる堀川で遡上を確認

名古屋市中心部を流れる堀川で今月上旬、清流で生息するアユが遡上(そじょう)しているのを堀川の浄化に取り組む市民団体「堀川1000人調査隊」が確認した。
昨年に続いての確認となり、同団体は「かつてはヘドロなどで魚もすめないような堀川が浄化されてきた証拠」と手応えを感じている。
アユの群れが確認されたのは9日、堀川の上流部にあたる同市北区の志賀橋と黒川橋の間で、オイカワなどの群れと一緒に泳いでいた。
同調査隊の服部宏事務局長によると、名古屋港付近の海で生まれたアユの幼魚が中区の納屋橋など中下流部を通って、10キロ以上遡上してきた可能性が高いという。
昨年も、打ち上げられていたアユ数十匹が確認されていたという。
清流でコケを食べながら生息するアユは「名古屋市版レッドリスト2025」では絶滅危惧2類に分類されている。
「なごや生物多様性センター」(名古屋市天白区)の担当者は「堀川では数年前から報告があった。餌となる石や岩に付着しているコケはなく、定着しているとは考えにくいが、アユが少しでも遡上する環境にはなってきている」と話している。
名古屋市河川計画課によると全長16.2キロの堀川は高度経済成長期の1966年には同市西区の小塩橋付近で、水質汚濁の目安とされるBOD(生物化学的酸素要求量)が、悪臭が発生するとされる目安の1リットルあたり10ミリ・グラムを大きく超える同54.8ミリ・グラムもあり「死せる川」と言われていた。
市ではその後、ヘドロの除去を進めたほか99年には堀川の再生を求める市民運動も盛り上がった。
庄内川の導水や雨水が一度に川に入り込まないよう雨水滞水池が整備されるなどの対策も取られ、浄化も進んだ。
2023年の調査では、BODは同4.2ミリ・グラムとアユが生息できる同3ミリ・グラム以下に近づいている。
07年から堀川の観察や調査を進めている同調査隊は約5万人が登録している。
服部事務局長は「多くの市民に関心を持ってもらっている。これからも行政とともに堀川の環境をよくしていきたい」と話している。
参照元:Yahoo!ニュース