現役教員27人の本音と葛藤「『指導したら損』という雰囲気」「日常の指導の先に『死』が」 カンニング後に命絶った生徒の両親「指導は必要と思っているが…」主張対立のまま裁判開始から1年
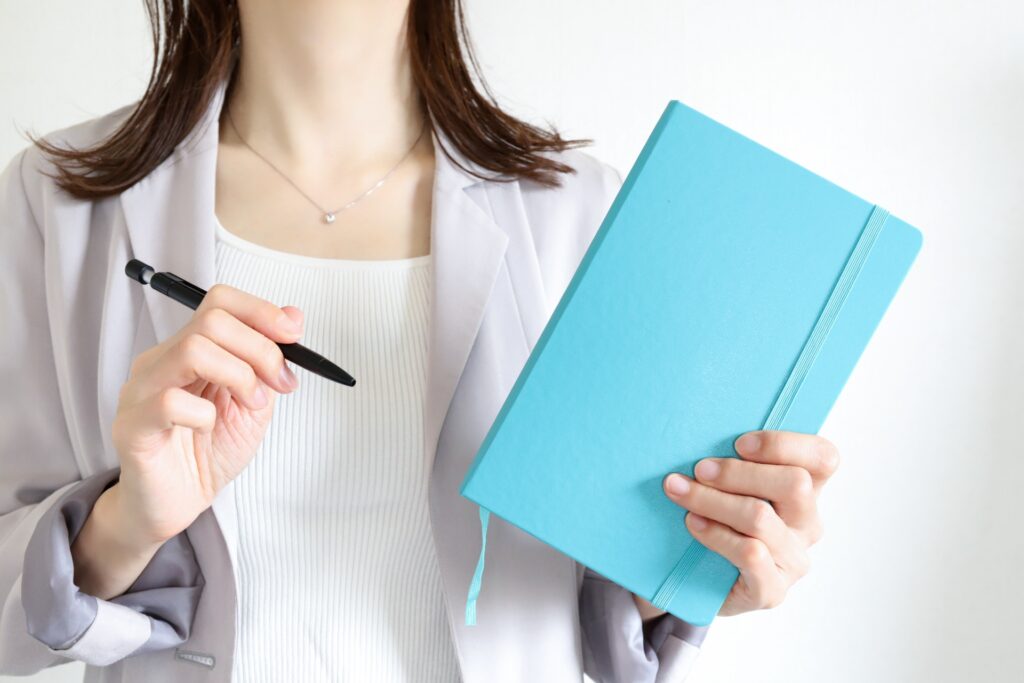
大阪の有名進学校で、男子高校生がカンニングの指導後に自殺し、両親が学校側を訴えている裁判は、双方の主張が真っ向から対立したまま、1年が過ぎた。
指導の直後に子どもの命が失われる事例が繰り返される中、生徒指導はどうあるべきか。
教育現場の本音とともに考える。
「私たちは、指導は必要だと思っているので、指導の仕方がどうかと問いかけたいと思っている」
4月24日、大阪地裁で行われた8回目の弁論の後、清風高校に通っていたユウトさん(仮名)の両親が語った言葉だ。
指導の直後に我が子を亡くした親が、それでも「指導は必要」だと声を振り絞り、指導の在り方を問うている。
ユウトさん(仮名)は、2021年12月の期末試験でカンニングが発覚し、両親によると、指導の中で教員に促される形で、自らを「卑怯者です」と言ったという。
全科目0点、8日間の自宅謹慎、写経80巻などの処分を言い渡され、指導の2日後、自ら命を絶った。
遺書には「死ぬという恐怖よりも、このまま周りから学校内から『ひきょう者』と思われながら生きていく方が怖くなってきました」と綴られていた。
学校側が設置した第三者委員会は、「『卑怯者』という表現など、指導には問題がある」と指摘した一方、「自殺の原因とは認定できない」と結論付けた。
両親は、生徒らへのアンケートが行われなかったことなどを理由に再調査を求めたが、学校側は拒否している。
2024年4月、両親は「不適切な指導が原因で息子は自死した」として学校側に賠償を求め提訴。
学校側は「同様の指導を受けた生徒が自死したことはなく、予測は困難だった。自らを『卑怯者』と言わせることはなかった」と主張。
裁判は1回目以降、非公開での弁論が続いていて、1年が過ぎた現在も双方の主張は対立したままだ。
不適切な指導をきっかけに子どもが亡くなることを、遺族らは『指導死』と呼ぶ。
教育評論家・武田さち子氏など専門家らの調査によると、「指導死」の疑いがある事例は、1989年~2022年で97件あったという。
相次ぐ“指導死”や遺族らの訴えなどを受け、文科省は2022年、生徒指導の手引き「生徒指導提要」を12年ぶりに改定。
「教職員による不適切な指導等が不登校や自殺のきっかけになる場合もある」と初めて明記された。
一方、「指導死」という言葉に対し、教育現場の受け止め方は様々だ。
女性教員(40代)「生徒の命は大切です。そう思っていない教師はいないと思います。指導する中で生徒たちが『指導死』という言葉を盾に、指導がやりにくくなったり、若い先生たちがやる気をなくしてしまうことを心配しています」
これは、取材班が独自に行った「生徒指導」に関するアンケート調査で、現役教員が綴った「本音」の1つだ。
アンケートは「現場で日々生徒と向き合う教員の声から、より良い指導の在り方を模索する」ことを目的に実施。
関西にある公立・私立高校5校の教員27人(20代~50代、教職員歴4年~37年、男性24人・女性3人)から回答が寄せられた。
以下、一部を抜粋して掲載する。
男性教員(50代)「起きた事案だけで判断せず、その行為に至った経緯や生育環境や最近の様子など、その背景を把握したうえで必要な指導を行うように心がけている」
男性教員(30代)「生徒が将来、社会で生きていくことができる力を身につけさせることを大切にしている。時代の変化もあり、社会や学校、生徒、保護者との関係をうまくつないでいくことに難しさを感じることがある」
女性教員(50代)「生徒、教師、保護者など関係するすべての人間の納得できる指導を心がけています。それぞれの立場や思いがあり、思うようにはならないこともある点が難しいです」
男性教員(50代)「ルールとマナーを守ること。まじめにがんばっている生徒がおろそかにならないこと。世の中や学校のルールよりも、個性というわがままを押し通す大人が増えたこと」
男性教員(40代)「強めに指導した後、次の日学校にちゃんと来てくれるか、真っすぐ家に帰るか不安になる」女性教員(40代)
「加害生徒から被害生徒を守るために腕を広げて教室の入り口をふさいだ時、腕の下を通り抜けようとした加害生徒の頭に腕が軽く当たりました。その時に『教師から暴力を受けた』と110番されたときには、暴力教師と言われて不安でした」
男性教員(30代)「生徒の顔色や保護者の顔色を気にしながら指導をしないといけない時代」
男性教員(40代)「本当にこのルールは必要なのか、それを守らせることはその子の将来に役立つことになるのだろうかと考えることはあります」
男性教員(20代)「生徒がこちらの意図と違う解釈をしていないか不安になることもある」
男性教員(30代)「正直学校現場は『指導したら損』という雰囲気もあります。生徒や保護者に強く追及され、頑張る人ほどつらい思いをしています。そのような(指導死という)言葉が広がれば、その空気が助長される気もします」
男性教員(40代)「多くの教員が経験のないことだけに、日常の指導の先に『死』があることに認識が足りていない教員もいると思う」
男性教員(50代)「指導することは教師の大切な仕事だと私は考える。この言葉が独り歩きし、指導=悪という印象になると、教師は指導しなくなる」
男性教員(30代)「死に追い込んでしまうようなものは指導とは呼べないと感じます」
女性教員(30代)「大人の言葉ですごく傷つき命を落としてしまう子がいるのは非常に悲しいことであってはならないと思います。指導する側はそんな気はなくても死を選んでしまうことを頭に入れて指導していく必要があると思います」
男性教員(40代)「当然あってはならないこと。その一方で、生徒が亡くなってしまった際に、教員の指導が“全ての”理由という風に語られるのは、少し違うような気がする」
23年前、担任をしていたクラスの生徒が指導の直後に亡くなる経験をした、青木俊也さん(62)が取材に応じた。
亡くなったのは、当時高校1年生だった西尾健司さん。
校内での喫煙が見つかり、教員から「お前は先生も親もみんなを裏切っている」と叱責されて無期限の謹慎処分になり、その日の深夜、自宅近くの建物から身を投げた。
その3か月前には、試験で友人に頼まれ自分の答案用紙を見せたことで指導を受けていた。
6日間の自宅謹慎処分で友人との連絡も禁止され、毎日反省文を書かされたが、母親の裕美さんは、「常に1日中反省していろと、まるで刑務所に入れられた感じがした。この頃からすごく様子が変わった」と話した。
指導に立ち会っていた青木さんは、「彼自身の日頃のことから考えても、そんな風に自ら命を絶つというのが想像できなかったので、『なんでや』と…」と当時の複雑な心境を明かした。
青木さんは、健司さんの母・裕美さんと対話を続け、自身の経験を若い教員に共有しながら指導の在り方を模索した。
その中で、「指導」は「支援」だと考えるようになった。
「教師が困ったと思う“困る子”というのは、きっとこの子は“困っている子”なのだろうと思うことができるようになった。その子の背景や、その子自身がどんなふうに感じているかということを、サポートする中で考えていかないといけない」と青木さんは話す。
現役教員へのアンケートでは、最後に、「生徒指導をより良くするために必要だと思うこと」について尋ねた。
男性教員(20代)「間違いなく教員はもっとアップデートしないといけない。そのために、『人権』をベースに考えた教員研修を地道に取り組んでいく必要がある」
女性教員(40代)「保護者の協力が必要。教師の人権や仕事も守ってほしい。生徒たちのために力や時間を注いでいる教師たちが責められることが亡くなることが必要。生徒の命や人権が守られないような指導は無くなってほしい」
男性教員(40代)「『生徒≧学校教員』の考え方ができれば良いのだが、『生徒<学校教員』が教育現場では自然になっている。そのためには、教員の心のゆとりも必要だと思うが、そうでない職場であることも事実」
男性教員(50代)「世の中や親は叱ることをまかせている気がする。そして、何事か起こればすべて教師のせいにして自分たちは悪くないという立場をとる。この質問を教師にすることがそもそも他人まかせの代表のようなもの」
男性教員(30代)「一人で指導を抱えて行うと、時に行き過ぎた指導に陥るケースもありえます。必要な指導をチームで行う体制作りが解決策の一つかと思います」
教員らの本音からは、指導の在り方を模索する前向きな姿勢と、様々な業務や保護者などとの人間関係の中で疲弊する現場の実態の両面が垣間見えた。
生徒の死を経験した青木さんだからこそ、至った考えもある。
青木さんは「まず、命を落とすことはあってはならないし、一番避けなければならない」としたうえで、「『今まであなたがやってきたこと、今ここにいる自分というのはすごく大事な自分だし間違ってなかったんやで。でも起こったことについては、それはよくなかったね』と、自信をなくさない伝え方をしていくことが大切だ」と話した。
「指導の在り方次第で救えた命があるかもしれない」と、そんな思いをする親や教員が一人でも減るために、相互理解や体制整備を進めながら、教育現場には諦めずに指導の在り方を追求し続ける姿勢が必要だ。
参照元:Yahoo!ニュース

