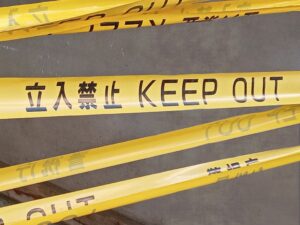マンション高層階から“小学生”が泥団子、頭部直撃の男性に「重傷・後遺症」を 加害者に“責任能力なし”被害者救済どうなる?
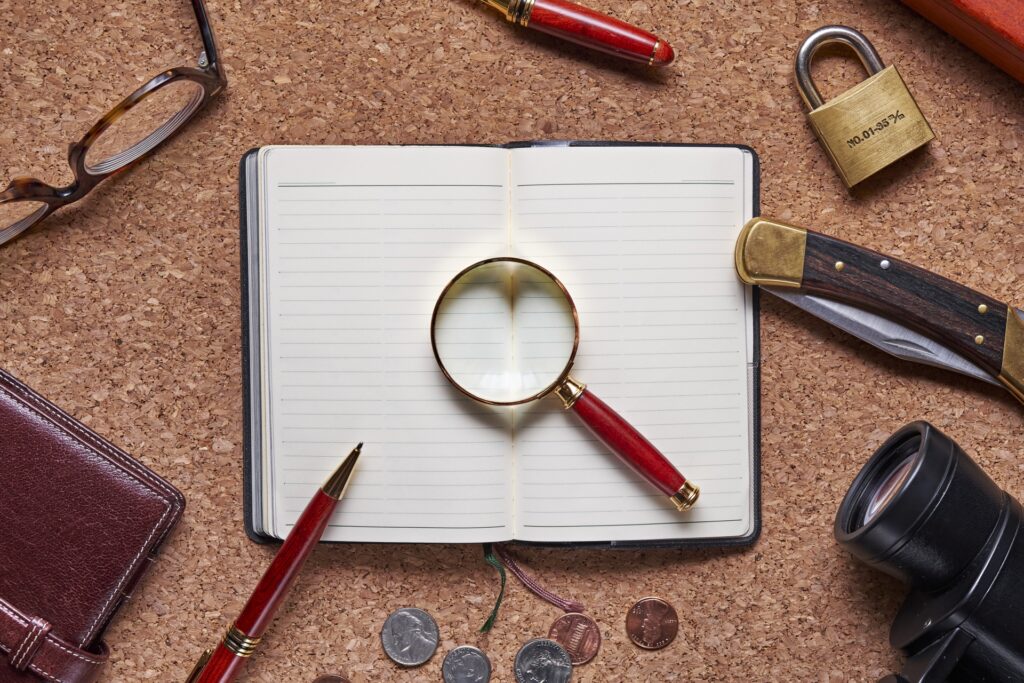
4月中旬、熊本県熊本市内のマンション駐車場で、男性が落下物の直撃を受け重傷を負った。
警察は事件の可能性も視野に捜査を進めていたが、今月16日、落下物は同マンションの高層階に住む小学生が投げた泥団子と判明したことが報道された。
当初、児童は泥団子を投げたことを否認していたものの、後に母親に対し自分の行為であることを認め、母親が警察に通報。
児童は「駐車場の先にある川に向かって投げたが届かなかった。下に人がいると分かっていた」と供述し、現場検証をしていた警察官や被害男性に水をかけた疑いも持たれている。
被害者の男性は、児童の母親から謝罪したいとの連絡を受けたが、後遺症に苦しんでおり、罪に問えない年齢の子どもの加害行為に対する複雑な心境を語っている。
報道によれば、警察は本件について殺人未遂の疑いもあるとして捜査していた。
仮に加害者が小学生ではなく成人の場合はどうなっていたのか、刑事事件および少年事件に詳しい杉山大介弁護士は次のように説明する。
「前提として、事件発覚後の手続きは異なるものの、成人であっても少年であっても、適用される刑法の内容自体が変わるわけではありません。今回のように、頭という体の重要な部分に物をぶつける行為は、人を死に至らしめる危険性があるという考え方もできます。そのため、殺人未遂罪の検討がまったく的外れというわけではありません。ただし本件では、当初何がぶつけられたか不明で、さらに報道によれば、落下物が『破裂した』という被害男性の話もあったため、警察が殺人未遂の可能性も視野に入れて捜査を始めたのだと考えられます」
泥団子は作ってから時間が経ったもので、陶器ほどの固さだったとも言われているが、「もし最初から『泥団子だった』と分かっていれば、殺人未遂の疑いは持たれなかった可能性が高い」(杉山弁護士)という。
20歳未満の者が事件を起こした場合、刑罰を受けるのではなく、家庭裁判所で更生を目的とした手続きがまず検討される。
とりわけ14歳未満の子どもは刑事責任能力がないと判断されるため、刑罰を科されることはなく、また当然に家庭裁判所に行くわけでもない。
このような子どもは「触法少年」と呼ばれ、警察から児童相談所へと通告される。
児童相談所は、その子の保護や健全な育成のために何が必要かを調査し、指導や一時保護、あるいは児童福祉施設への入所といった措置を検討することになる。
事件が重大な場合や、より専門的な判断が必要と判断された場合は、児童相談所から家庭裁判所へ送致されることもある。
家庭裁判所では、審判を経て保護観察や少年院送致などの保護処分が決定される可能性があるが、いずれにしても刑罰が科されることはない。
これは、子どもが未熟であるという考えに基づき、刑罰よりも支援と育成を重視する考え方によるものだ。
今回の加害児童についても、「触法少年」として児童相談所に通告されたと報道されている。
報道されている事情から、今後の展望について質問すると、杉山弁護士は次のように回答した。
「そもそも、当該児童がどのような目的で、どのような方法で泥団子を投げたかといった『行為の悪質性』については、今後の事実認定によって変わる可能性があります。結果として被害が重かったものの、児童自身が自らの行動の危険性を十分に理解していなかった、という背景も考えられます。また、今回は児童本人が保護者に告白し、保護者がその告白を受けて警察に届け出ている様子が見られることから、児童本人や保護者の性質について、その可塑性を否定するような大きな問題があるとは言いがたい、と判断される可能性が高いでしょう。このような状況から、家庭裁判所に送致され、さらに重い処分が下されるといった展開は、あまり想定されません」
少年事件のもっとも大切な部分は、処分を下すまでの過程でさまざまな情報を引き出し、将来同じような問題が起きないよう、子どもをケアすることにある。
「そのため、『最終的な処分が重いか軽いか』という点について論じること自体、少年事件の本来の目的とは少し異なります。十分な問題への対処がとれたから、処分が軽かったり不要になっていたりする場合もあるわけです」(同前)
加害児童に刑事責任は問えないものの、冒頭で触れたとおり、被害者は重傷を負い、後遺症にも悩まされているという。
もし被害者が損害賠償を求める場合、誰に請求することになるのか。
杉山弁護士は「今回のケースでは、加害児童が小学生であるため、民事上も責任無能力者と判断される可能性が高い」として、以下のように続ける。
「刑事と異なり、民事では年齢で責任能力を区切っているわけではありませんが、小学生であれば通常、自分の行為がどのような結果を招くかを十分に理解する能力がないとみなされることが多いです。そのため、民法714条に基づき、監督義務者である保護者に対して損害賠償を請求するのが一般的です。この民法の条文には、監督義務を怠らなかった場合には責任を免れるという但書がありますが、実際にこの主張が認められるのは非常に難しいのが実情です」
保護者が監督義務を怠らなかったと証明するハードルは高く、多くの場合、その責任が認められやすい傾向にあるという。
「法律は、実際に損害が発生しているのに誰も責任を負わないという状況をあまり望ましいとは考えていません。そのため、子どもが起こしたことによって生じた被害に対して、もっとも賠償能力があり、かつ監督する立場にある保護者が責任を負うべきだと判断されることが多いのです。したがって、今回のケースで被害者の方が損害賠償を求める場合、加害児童本人ではなく、その保護者に対して請求するのがもっとも現実的な選択肢となります」(同前)
繰り返しになるが、児童の投げた泥団子によって被害者は後遺症をともなう重傷を負っており、その苦痛は計り知れない。
法的な側面から見ると、責任能力のない子どもの行為に対し、現行の法制度がどのように対応し、そして被害者の救済をどう図っていくのかという、複雑で繊細な問題が浮き彫りになったと言えるだろう。
参照元:Yahoo!ニュース