アップルの「中国デトックス」、痛みは避けられず
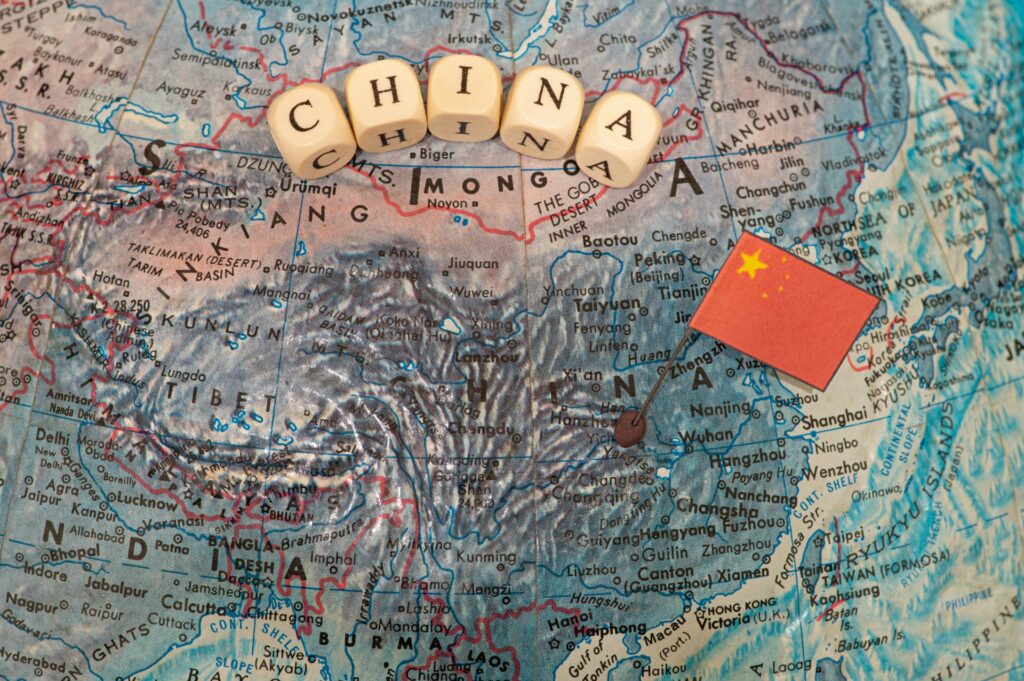
アップルをパソコン業界のニッチ企業から世界屈指の大企業へと変貌させたiPhoneの成功は、中国のサプライチェーン(供給網)に負うところが大きい。
しかし現在、地政学的緊張と貿易戦争により、その依存関係が再考を迫られている。
英フィナンシャル・タイムズ紙でアップルを取材してきたパトリック・マギー氏が執筆した「Apple in China(中国におけるアップル): 世界最大企業の掌握」は、同社の台頭に中国が果たした役割に焦点を絞った著作だ。
元幹部やエンジニアを含む200人以上のインタビューや資料を基に、同社が製品のほとんどを中国サプライヤーに依存し、昨年時点で売上高の17%を中国の消費者から得るに至った経緯を迫真の筆致で描いている。
アップルの中国進出は、台湾の電子機器受託生産大手、富士康科技集団(フォックスコン)の存在抜きでは不可能だった。
同社とその競合他社は、1990年代半ばに中国本土に工場を設立することで、中国の輸出主導型モデル形成に重要な役割を果たした。
それができたのは、地元当局と「手を取り合って」働いたこと、そして補助金やインフラ、低コストの出稼ぎ労働者のおかげだ。
アップルが「アンクル・テリー」と呼んだフォックスコンの創業者、郭台銘(テリー・ゴウ)氏は、その政治的手腕ゆえに抜きんでた存在だったとマギーは記している。
アップルは1999年にフォックスコンと緊密な提携を開始し、まずはiMac(アイマック)、そして数年後にはiPodの生産を委託した。
迅速かつ大規模なフォックスコンの生産能力のおかげで、2005年のiPod出荷台数は2250万台と、03年の100万台弱から急増した。
中国に進出した他の多国籍企業と異なり、アップルは現地に完全子会社や合弁企業を設立しなかった。
代わりに多くの現地企業に投資し、部品の供給方法やアップル製品の製造方法を教えた。
これにより同社は少数の主要サプライヤーへの過剰依存を回避し、交渉で強い立場に立つことができた。
また、マギー氏の著書に引用された中国生まれのエコノミスト、イー・ウェン氏の発言によると、こうしたやり方は「モノ作りの技術、実務の組織化、生産、流通、移動、コミュニケーション、消費」に関するノウハウの巨大な移転をもたらした。
中国における世界最先端の製造サプライチェーンの発展と、華為技術(ファーウェイ)から小米科技(シャオミ)に至るスマートフォン・ブランドの誕生を後押ししたのはアップルだと言っても過言ではない。
この戦略は台湾企業に代償を強いた。
アップルの支援により、同社のサプライチェーンは次第に「赤く」なり、中国本土の企業グループがますますシェアを拡大していった。
しかし習近平氏が2012年に国家主席となって以来、中国指導部は国家による経済支配を強化し、その影響は民間部門や外国多国籍企業にも及んでいる。
中国は15年、外国の技術からの脱却を目指す「中国製造2025」計画を発表した。
中国事業を取り巻く政治的リスクが高まる兆しがあったにもかかわらず、アップルのティム・クック最高経営責任者(CEO)はますます中国に傾注した。
トランプ米大統領が仕掛けた貿易戦争は、この関係を覆す可能性がある。
これまでのところ、中国は米国との関係が悪化する中でもアップルに対する報復措置を控えており、それには十分な理由がある。
例えばクックCEOによると、アップルは中国国内で500万人の雇用を支えており、その半分以上は製造業だ。
また中国が大手外国企業を標的にすると他の投資家を怖がらせ、ビジネスに開かれた国だという言い分が崩れてしまう。
中国は依然として欧米の技術と資本を必要としている。
米中両国は12日、大半の関税措置を停止した。
しかし、中国1国に製造を依存するアップルのモデルが持続不可能であることは明白だ。
クック氏はサプライチェーンの多様化を加速させており、第3・四半期までに米国向け製品の「大多数」をインドとベトナムで製造する見込みだと述べている。
同社はまた、「投資を米国に戻す」というトランプ氏の呼びかけに応えるため、今後4年間で米国に5000億ドル以上を投資すると約束している。
長期的に見れば、これは関税を考慮しなくてもコスト上昇を招くだろう。
例えば、インドでのスマホ製造コストは中国を最大10%上回る可能性があると、ロイターは先月報じた。
米国での製造はさらに非現実的だ。
ウェドブッシュ・セキュリティーズのアナリスト、ダン・アイブス氏は、米国でiPhoneを製造すれば価格は現行の3倍以上の3500ドルになると試算している。
時間の経過とともに、アップルの製造拠点は米電気自動車(EV)大手テスラに似てくるかもしれない。
テスラは米国、ドイツ、中国に工場を分散させている。
より不透明なのは、中国サプライヤーへの支援と投資を継続することを米政府が容認するかどうかだ。
ルビオ国務長官はかつて、アップルと中国のメモリー半導体企業、長江存儲科技(YMTC)との提携計画について、アップルが「火遊びをしている」と警鐘を鳴らした。
この計画はその後撤回されている。アップルが人工知能(AI)分野に進出し、テスラが人型ロボット開発に注力する中、米政府は両社の中国事業を注視するだろう。
アップルには、遅ればせながら「中国デトックス」を実現する時間的余裕があるかもしれない。
とは言え、その過程は苦痛を伴うものとなるだろう。
参照元:REUTERS(ロイター)

