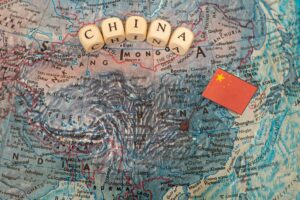ミャンマー大地震、金目当ての偽ニュース・動画が拡散

ミャンマーで3月に起きた大地震の後、混乱に乗じて営利目的でソーシャルメディア(SNS)に偽のニュースや動画を投稿する動きが広がっているとデジタル活動家らが警告している。
センセーショナルな画像、偽の救出劇の演出などによって恐怖心をあおったり、関心を高めたりし、閲覧者が多い場合には作成者は数万ドルの広告収入を得る可能性もある。
シンクタンクのブルッキングス研究所のシニア・テクノロジー・リサーチャー、ダレル・ウエスト氏は「偽の情報で金儲けをしている連中がいることを認識すべきだ」と訴える。
また、「オンラインのコンテンツを規制している法律はほとんどなく、IT企業は人々の保護にあまり取り組んでいない」と問題視した。
国営メディアによると、3月28日に発生したミャンマーの地震による死者数は3600人を超え、負傷者は約5000人に達し、数百人が行方不明となっている。
ミャンマーは10年間の発展と不安定な民主主義を経て、2021年のクーデターで軍が権力を握って経済が壊滅。
この地震は人口5300万人の貧困にあえぐ東南アジアの国にとって、大きな打撃となった。
ミャンマーでの誤報やヘイトスピーチに対抗するフェイスブックページを運営する草の根団体「デジタル・インサイト・ラボ」は、シリアやマレーシアで撮影された動画や、人工知能(AI)で作成された動画が拡散していると述べた。
身の安全のためにペンネームを使っている研究員のウィンディ氏は「これらの投稿の多くは、過去の無関係な事件の写真や動画を再利用したり、AIが生成したコンテンツを利用して虚偽のストーリーをねつ造している」と指摘する。
デジタルの専門家の話では、大災害後のSNSでは、誤ったキャプションがつけられた画像、偽の動画、救助活動に関する虚偽の物語など、誤情報や偽情報が多く発生する。
国連防災機関(UNDRR)の広報責任者、ジャネット・エルズワース氏は「誤情報や偽情報が流布するとパニック状態に拍車がかかり、避難が遅れ、緊急サービスへの信頼を損なう恐れがある」と懸念する。
昨年9月に、大型ハリケーン「へリーン」が米国の一部に壊滅的な被害をもたらした際、政府が連邦災害基金を不法移民に横流ししていると非難するデマが広まった。
2023年の大地震でトルコとシリアで計5万1000人を超える死者が出た際には、過去に撮影された日本やグリーンランドの津波の動画を投稿し、それを被災地からのリアルタイム映像と偽る動きがあった。
「今や、事実上何でもありの無法地帯だ。オンライン上のコンテンツを規制する法律はほとんどなく、テクノロジー企業は人々を守るためにほとんど何もしていない」と、ブルッキングス研究所のウェスト氏は述べた。
IT政策グループのホワット・トゥー・フィックスによると、SNS運営会社とコンテンツクリエイターが24年に得た広告収入は、200億ドル(約3兆円)を超えた。
ミャンマーの地震を巡る虚偽情報を監視している団体の創設者、ビクトワール・リオ氏は、コンテンツクリエイターはフェイスブックやインスタグラム、ティックトックなどを利用し、投稿と一緒に表示される広告から収益の一部を得ていると指摘する。
たとえ虚偽の内容や、AIが生成した虚偽のコンテンツでも、閲覧回数が伸びるほど収入を多く得られる仕組みだ。
正確な金額を算出するのは難しいものの、21年のミャンマーでのクーデターといった過去の有事では、こうした「詐欺師」らは数万ドルを稼ぐことができたとリオ氏は指摘する。
ファクトチェック会社ニュースガードと分析会社コムスコアの21年の調査によると、誤情報ウェブサイトは毎年デジタル広告から26億ドルの利益を上げているという。
ホワット・トゥー・フィックスによると、フェイスブックとインスタグラムを所有する米メタはソーシャル広告市場の60%以上を占め、2024年には310万以上のクリエイターのアカウントがあり、前年比で55%増加している。
「ミャンマーの現状では、出回っている偽情報の大部分は金銭目的だ」とリオ氏は語った。
メタは、ポリシーに違反する投稿を削除し、パートナーと協力して虚偽の内容を否定し、そのような投稿をフィードの下に移動させることで「目にする人がより少なくなるようにしている」と主張する。
メタは今年1月に米国でファクトチェックのプログラムを廃止し、政治的コンテンツの管理方法を変えた。
ティックトックの運営会社は、プラットフォーム上で誤解を招くような虚偽のコンテンツを禁止し、ミャンマー地震後には不正確な投稿を積極的に削除し、ユーザーを信頼できる情報源に誘導していると述べた。
同社は、50以上の言語で活動する、訓練を受けたモデレーターとファクトチェックのパートナーがいると述べた。
また、リオ氏は、インターネットの遮断によりミャンマーから発信される情報が少なくなり、誤報が広がっていると述べた。
「国外からフェイスブックにアクセスし、情報を得ようとしている人々の巨大なコミュニティーがある。彼らは必死に情報を探しているため、誤報に特に弱い」と解説する。
ミャンマー国内のインターネット遮断を監視しているミャンマー・インターネット・プロジェクトの責任者、テイク・テイク・アウン氏は、この状況は人命を危険にさらしていると語った。
「ユーザーの興味をひいてクリックさせる性質と、SNSのアルゴリズムの機能によって(偽情報の投稿が)ニュースフィードのトップに来る。その結果、人々が質の高い情報にアクセスすることがより困難になる」と分析。
「偽情報が多くの救援活動の妨げになっている。この時期の情報へのアクセスは命に関わる重要な問題だ」と問題視した。
デジタル権利団体「アクセス・ナウ」の上級政策アナリスト、エリスカ・ピルコバ氏は、プラットフォーム各社は、偽コンテンツが掲載された後に報告を待つのではなく、誤情報を阻止するためにもっと努力すべきだと述べた。
「情報へのアクセスは常に生命線であり、特に危機的状況においてはなおさらだ。そのため、(プラットフォームには)非常に厳格なデューデリジェンス義務が課せられる」と主張する。
政府にも対策強化が求められている。
欧州連合(EU)はIT企業の規制を目指しているのに対し、米国は自国企業の世界市場での支配力を加速させるためにいくつかの権利保護的な規制を撤廃した。
UNDRRのエルズワース氏は、偽ニュースの流布防止に取り組むにはIT企業や政府の努力だけでは足りないとし、宗教指導者や市民社会、地元メディアも役割を果たすよう求めた。
「誰もが参加しなければならない」と彼女は言う。
「重要なのは、どの立場の人も自分に必要な行動をとれるように力を与えることだ」。
参照元:REUTERS(ロイター)