地震と大雨で二重被害の男性「もうどうでもいいと思ってしまう」能登被災者に長期的な心のケア必要
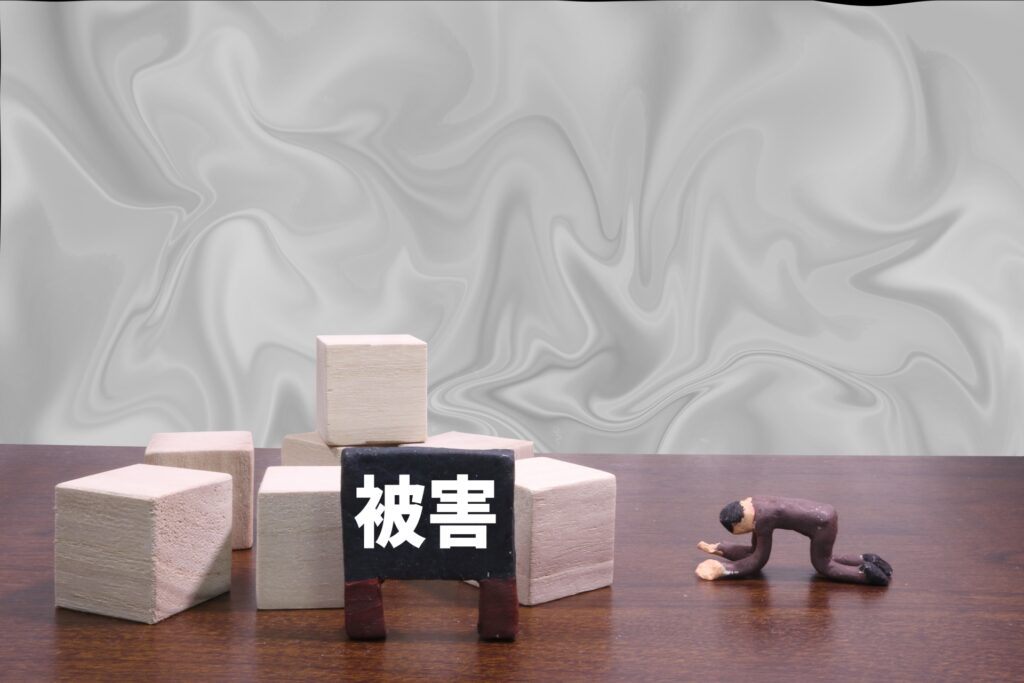
「この怒りや悲しみをどこに向けていいのかわからない」。
元日の地震と9月下旬の大雨の被害を受けた石川県珠洲市の男性(77)は、胸の内を明かす。
地震で両隣の家が自宅に倒れかかった。大
雨で自宅周辺が泥で埋まり、今も手つかずだ。
10月に入居予定だった仮設住宅も水につかり、入居できたのは今月14日。
「もうどうでもいいと思ってしまう」と、進まない復旧にいら立ちを募らせる。
被災地で心のケアにあたる金沢大の菊知充教授(精神行動科学)は、不可抗力の挫折が続き、無気力になってしまう「学習性無力感」が被災者に表れていると指摘する。
元日が近づき、被災の記憶がよみがえって心身に不調をきたす「アニバーサリー(記念日)反応」を招くことも心配する。
ボランティアで珠洲市や輪島市の仮設住宅や避難所を回る精神科医の林正男・穴水こころのクリニック院長によると、地震後、飲酒量の増加でトラブルを起こしたり、一人暮らしで認知症が進んでしまったりする高齢者が目立つようになった。
環境の変化で部屋に籠もりがちになったことが影響しているとみられる。
大雨で被害を受けた住民には自分ばかりが被害を受けることへの怒りといった負の感情を抱く人も増えているという。
林院長は「無理に感情を抑えると、精神に不調をきたしてしまう場合もある。話すことで心を落ち着かせつつ、様子を見ていくしかない」と話す。
子どもへの影響も懸念される。
輪島市の女性(40)は、大雨で自宅1階に水が入り込み、小学3年生の長男が「死にたくない」とパニックになった。
「地震後、トイレに1人で行くのを怖がるようになり、夜の眠りも浅いようで心配だ」と話す。
文部科学省は1月26日~7月19日、珠洲、輪島、能登3市町の小中学校にスクールカウンセラーを派遣した。
面談した子どもからは「不安で眠れない」「授業に集中できない、落ち着かない」といった声が多く聞かれたという。
石川県は今年度、奥能登4市町の小中高に配置するスクールカウンセラーを前年度から2倍の20人に増員した。
東日本大震災では、文科省が被災7県の子どもについて、2012年に調査したところ、14.1%に「物音に敏感になったり、イライラしたりするようになった」などの心的外傷後ストレス障害(PTSD)が疑われる症状がみられた。
被災者の心の傷は長期にわたる。
震災で被災した宮城県七ヶ浜町での東北大による継続調査では、大規模半壊以上の家屋被害に遭った住民でPTSDの兆候がみられたのは3年間で3割超だった。
不眠の傾向がみられた割合は、仮設住宅から災害公営住宅に移り始めた後の15年度に増加に転じた。
調査した富田博秋教授(精神神経学)は「人間関係を築いた場所から新たな環境に移り、孤立感が強まったため」と分析する。
被災者の心を支えるため、石川県は「石川こころのケアセンター」(金沢市)から、精神科医や保健師らを被災地に派遣し、来年3月までに輪島市内にも拠点を設置する。
能登はこの1年、暮らしも、心も、街も傷を負った。
変わらぬ景色、進まぬ復旧に疲弊の色を見せる被災者は少なくない。
復興への道筋をどう描くか。
人口流出、高齢化が進む能登に、時間的猶予はない。
参照元∶Yahoo!ニュース

