「赤鬼」とはやしたてられ 差別や偏見に苦しみ、隠れるように生きて 被爆者が立ち上がるまで
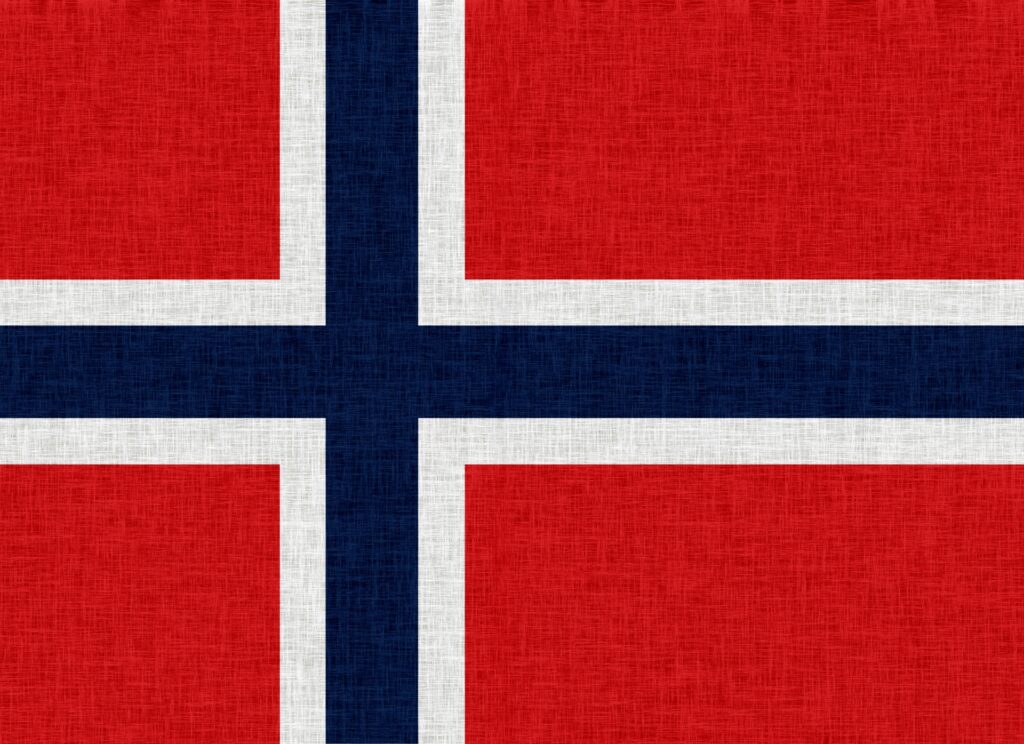
ことしのノーベル平和賞の授賞式が10日、ノルウェーの首都オスロで開かれた。
受賞したのは全国の被爆者組織から成る日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)。
1945年の被爆から11年後の1956年に結成され、「ふたたび被爆者をつくるな」を合言葉に国内外で核兵器廃絶を訴えてきた。
米軍が投下した原爆は、その年のうちに広島で約14万人、長崎で約7万人の命を奪ったと推計されるが、生きながらえた者たちも心身に深い傷を負い、肉親や財産を失い、苦難の道を歩んだ。
日本被団協の運動は、「ほかの誰にも同じ思いをさせてはならない」という被爆者たちの切実な思いに突き動かされてきた。
わらにもすがる思いで 「ばかにされ、傷つきながらも活動してきました。世界に私どもの声が伝わったと思うと嬉しかった」。
広島市の高齢者施設で暮らす阿部静子さん(97)は穏やかに語る。
日本被団協の結成時を知る、いまや数少ない被爆者である。
「闇夜に荒波に向かって叫ぶような気持ち、わらにもすがるような気持ちでやってきました」。
傷病や生活困窮にあえぎ、差別や偏見にもさらされた被爆者が立ち上がった前史に思いをはせる。
「赤鬼」とはやしたてられ被爆から32年の1977年、自宅で被爆者運動への思いを語る50歳の阿部さん 1945年8月6日。
結婚間もない18歳だった。
当時暮らしていた中野村(現安芸区)から勤労奉仕に動員され、爆心地から約1.5キロの場所で建物疎開作業中に被爆した。
民家の屋根の上で強烈な熱線を浴び、10メートルほど吹き飛ばされ、しばし意識を失う。
「気が付いた時には辺りにほこりが舞って薄暗く、皮膚が焼けるような変な臭いがしました」。
顔や腕を焼かれ、右腕は爪の先までずるりと皮がむけてぶらさがっていた。
命からがら8キロの道のりを歩いて逃げ帰り、母と姉の懸命な看病で一命は取り留めたものの、やけどした皮膚は盛り上がり、真っ赤に腫れた。
痛みは引いても、目や口が引きつり、うまく食べることもできない。
「右腕は焼け縮み、左腕と比べて10センチくらい短くなりました」。
日常生活もままならない状態が続いた。
南方に赴いていた9歳上の夫の三郎さん(1992年に73歳で死去)の陰で、同居の義母には離婚を迫られもした。
敗戦から4カ月たった年の暮れ、三郎さんが復員。
変わり果てた妻の姿に顔色一つ変えず、「自分も戦地で手足を失っていたかもしれない」と優しく寄り添った。
それでも、外に出れば周囲から奇異の目で見られ、近所の子どもには「赤鬼」とはやしたてられた。
原爆さえなければ、戦争さえなければと思う日々。
「焼かれた顔や腕は元には戻りません。ふた目と見られん姿になり、体も不自由で勤める先もない。姑には嫌みを言われ続け、うつむいて、隠れるように生きてきました」
ある夏、原爆ドームそばのバラックで「原爆被害者は声を掛けてください」と書かれた看板を見かける。
熱線で一面ケロイドとなった自らの背中をさらして原爆への怒りを訴え、「原爆一号」と呼ばれた吉川清さん(1986年に74歳で死去)がいた。
吉川さんはそこで土産物店を開き、請われて傷痕も見せた。
「原爆を売り物にしている」と非難されもしたが、原爆の恐ろしさを知らしめるために奔走した。
社会の片隅で暮らす被爆者を訪ね歩いて生活実態を聞き取り、1951年には被爆者組織「原爆傷害者更生会」を結成。
翌年には原爆詩人として知られる峠三吉さん(1953年に36歳で死去)らと「原爆被害者の会」をつくった。
被爆者組織の草分けだった。
「ケロイドを気味悪がられ、銭湯で断られた被爆者のために吉川さんは自宅の風呂を沸かして被爆者に入らせたりしていました」と阿部さんは目を細め、回想する。
吉川さんと妻の生美さん(2013年に92歳で死去)とはその後も家族ぐるみの付き合いになった。
初の国会請願へ1956年3月、藤居平一さん(中央)を代表に初めての国会請願をした原爆被害者たち。
被爆から10年余りたった1956年3月、被爆者たちは初の国会請願を行う。
広島・長崎から約50人が東京に出向き、政府閣僚や国会に切実な声を届けた。
率いたのは、後に日本被団協の初代事務局長となる藤居平一さん(1996年に80歳で死去)。
傷つけられた体や奪われた命に対する原爆被害者の悲痛な声を「まどうてくれ(元通りにしてくれ)」と表した藤居さんは「あの日」、東京にいて被爆を免れた。だが銘木店を営む実家は広島市中心部にあり、父や妹を失った。
敗戦後、古里で家業を再建しながら民生委員を務め、原爆被害者の窮状を知る。
やがて家業が傾くほどに被爆者救援と原水禁運動に心血を注いだ。
国会請願には、被爆者の会に出入りしていた阿部さんにも声がかかる。
当時3人の子の母。
家のいっさいを義母に頼むわけにはいかず、6歳の次男を連れて参加。
窮状を訴え、被爆者救済を求めた。
しかし「色よい返事は得られず失望が強かった。きちんとした組織をつくって訴えなくてはとなりました」。
疲れ切って広島に帰る夜行列車の車中、阿部さんは紙切れに詩をつづり、藤居さんに手渡す。
「悲しみに苦しみに/笑いを遠く忘れた被災者の上に/午前十時の陽射しのような暖かい手を/生きていてよかったと思いつづけられるように」
「生きていてよかった」と思う日が来るまで訴え続けなくては―。
詩は被爆者たちを勇気づけた。
ばらばらに活動していた被爆者の組織を藤居さんらがまとめ、56年5月に広島県被団協が結成。
長崎でも6月に長崎原爆被災者協議会ができた。
そして8月10日、長崎市で開かれた第2回原水爆禁止世界大会の2日目の夜。
長崎国際文化会館での原水爆被害者全国大会で、日本被団協は産声を上げた。
「今日までだまって、うつむいて、わかれわかれに、生き残ってきた私たちが、もうだまっておれないで、手をつないで立ち上がろう」。
全国から集まった800人の中に阿部さんもいた。
〈私たちの体験をとおして人類の危機を救おう〉―。
代表委員に選ばれた森滝市郎さん(1994年に92歳で死去)が、日本被団協の結成宣言「世界への挨拶」を読み上げた。
その中には阿部さんがつづった詩の中の言葉も。
壇上には原水爆禁止、被害者への国家補償がスローガンに掲げられていた。
ノーベル平和賞の受賞演説で、日本被団協代表委員の田中熙巳さん(92)は、被団協の運動の歩みを語り、被爆者が核兵器廃絶と共に求めてきた国家補償について説いた。
被爆者たちは、なぜこのような原爆被害がもたらされたのか、その責任のありかを追及し、二度と戦争を起こさない、二度と核を使用させないための道筋を探ってきた。
だが、「核兵器はなくなっているわけではなく、むしろ今一番危険を感じています」と阿部さん。
「ノーベル平和賞はこれまで頑張ってきた先達へのご褒美であり、いま生きている被爆者や、その心を継ぐ人にとっては、もっと頑張れというメッセージだと思っています」
日本被団協へのノーベル平和賞授与が発表されたとき、取材を通して知り合い、すでに世を去った多くの被爆者の顔が次々頭に浮かんだ。
被団協で被爆者運動の前線にいた人もいれば、ひとりの人間として教訓を伝えるため、若い世代に記憶を語っていた被爆者もいる。
思い出すのもつらい体験を、記者に「伝えて」と語ってくれたのは、人類が二度と同じ過ちを繰り返さないようにという強い思いからだ。
むろん、被団協は、平和賞を受賞するために運動してきたわけではない。
だがこれによってあらためて個々の被爆者の存在や、核が人類に何をもたらすのかという現実に、世界の目が向けられることにつながるなら、うれしく思う。
ただ世界は今、核兵器を持つ国の脅しや戦争という暴力にまみれている。
ひとたび戦争になれば、ひとたび核兵器が使われれば、その傷は長く深く続く。
きのこ雲の下にいた被爆者は、それを身をもって教えてくれている。
同時に、戦争や核使用の主体である国家の責任についても考えさせる。
阿部さんが絞り出すように語ってくれた言葉を、あらためて胸に刻む。
参照元∶Yahoo!ニュース

