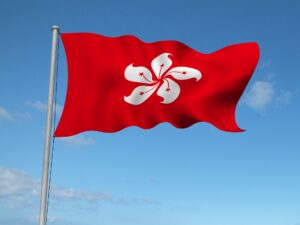地熱発電の開発促進へ、国が掘削調査し支援 多額の費用や地元との調整を肩代わり

経済産業省は、再生可能エネルギーの拡大に向け、国内資源が豊富な地熱発電の開発を促す新たな支援に乗り出す。
多額の調査費用や、地元との調整の難しさがネックとなっているが、民間に代わって国が掘削調査を行うことで、参入障壁を低くする。
年度内に改定する予定の次期エネルギー基本計画にも、地熱発電の開発促進や国の支援方針を盛り込む。
新たな支援策では、政府系の独立行政法人「エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)」が初期調査を手がける。
地表温度などを基に、地熱発電に適した場所を探し出し、掘削や地下構造の確認まで行う。
地元との協議も政府主導で行い、商用化の見通しが立つと判断すれば、事業者を公募する。
2025年度に候補地の選定を進め、早ければ26 年度にも調査を始める。
26年度の当初予算で必要な財源を確保する考えだ。
地熱発電は、地中深くのマグマで熱せられた蒸気でタービンを回す発電方式だ。
火山国の日本は、資源量が米国(30.0ギガ・ワット)、インドネシア(27.8ギガ・ワット)に次いで世界3位の23.5ギガ・ワットと豊富だ。
だが、開発が制限される自然公園内に資源が集中していることもあり、現在運転している地熱発電の出力は0.6ギガ・ワットにとどまる。
新たに地熱発電所を建設するには、地下1000~2000メートルを掘り下げて蒸気の噴出量を確かめる必要があり、初期調査だけで10億円以上の費用がかかる。
掘削しても噴出量が足りずに事業を停止するなど、成功率は3割程度にとどまる。
現在は掘削費用の最大3分の2を補助する制度があるが、失敗した場合、補助分以外は全て企業の損失となってしまう。
噴出量が十分でも、温泉地近くの場合は、湯量や泉質への影響を懸念する温泉業者から反対されるケースもあり、開発事業者が二の足を踏む要因となっていた。
国が掘削調査や地元との協議を担うことで、従来より手続きをスムーズに進められる可能性が高まる。
地熱発電は、太陽光や風力に比べ、天候に左右されずに24時間安定して稼働できる再生エネとして、純国産の「ベースロード(基幹)電源」になると期待されている。
政府は30年度に電源に占める割合を1%とする目標だが、現状では0.3%にとどまる。
再生エネに占める割合もわずか1.4%にすぎない。
次期エネルギー基本計画で定める40年度の電源構成では、地熱発電の拡大などで再生エネが現計画の「36~38%」から引き上げられ、火力発電を初めて上回る見通しだ。
参照元∶Yahoo!ニュース