寒暖差で10月急増「咳ぜんそく」 秋に要注意“長引く咳” ほかの病気が潜んでいるかも
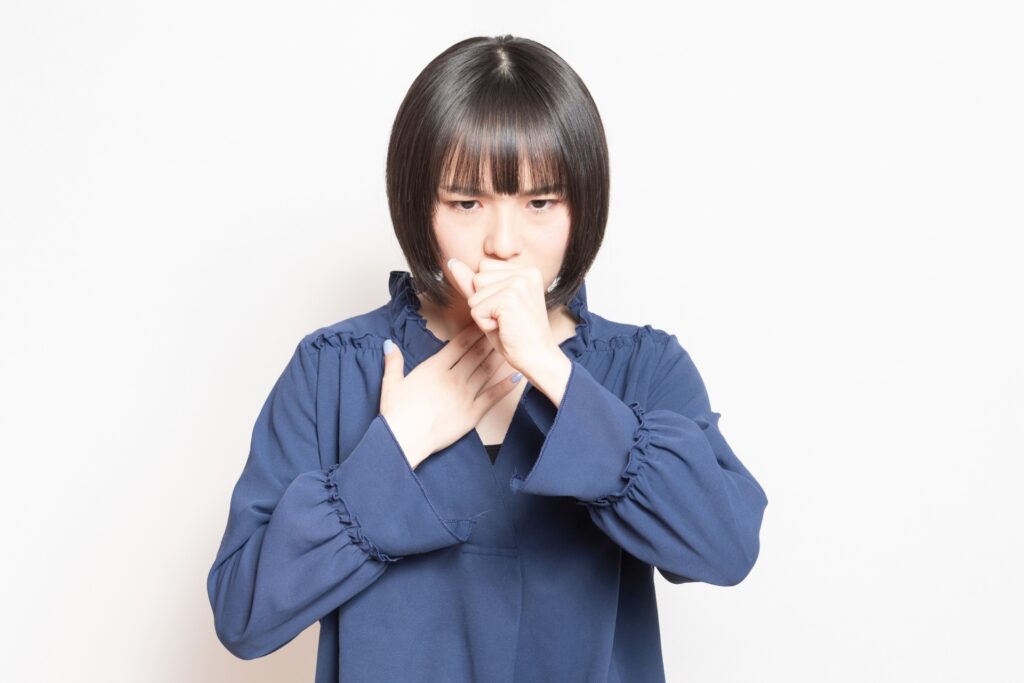
朝晩と日中の寒暖差が大きくなって、体調を崩しやすくなってる。
寒暖差が大きくなる10月に増えるのが、「咳ぜんそく」という症状だ。
10月2日は最高気温と最低気温との差が9.9℃あった。
4日も寒暖差が8.1℃、7日は9.2℃、8日は10.2℃だった。
12日からの3連休も、10℃前後の寒暖差が予想されている。
池袋大谷クリニック 大谷義夫院長「寒暖差が7℃以上あると、体調を崩しやすくなる。その日の気温差だけでなく、前日との気温差や室内外の温度差も、体の負担になる」
60代の男性「寒暖差が大きいと、ダルさ、疲労感、イライラしやすくなる」
60代女性「秋口など季節の変わり目になると、腰やひざの関節がひどく痛む」
40代女性
「寒暖差で、花粉症みたいな咳やくしゃみ、鼻水が止まらなくなることがある」
松岡アナ「ここ数日、のどに痛みが。のどが渇くと咳が出そうになる」
池袋大谷クリニックでは、10月の患者の8割を超える人が「咳ぜんそく」だそうだ。
「咳ぜんそく」は、風邪や寒暖差などをきっかけに気管支が炎症を起こし発症する。
ちょっとした刺激で咳き込み、一度出だすとしばらく止まらない。
寒暖差で「咳ぜんそく」が増える理由。
冷たい空気を吸うことで、気道のアレルギー、免疫反応が誘発され、気管支が炎症を起こすためだ。
30代の女性「10年前、風邪をひいたことをきっかけに、咳ぜんそくになりました。 毎年10月ごろになると、咳ぜんそくを発症します。会議で発言する時など、咳を我慢するのがつらい」といいます。
60代の男性「秋口から寒暖差で咳が出るようになり、たんも絡む」ようです。「 深呼吸すると息が吐きづらい」そうです。
咳ぜんそくが悪化すると、呼吸困難を伴う「気管支ぜんそく」になる場合もあります。
咳ぜんそく含め、ぜんそくによる日本国内の死者数は、年間1000人以上にのぼっている。
池袋大谷クリニック 大谷義夫院長「咳が2週間以上続いたら、医療機関を受診するように。咳ぜんそく以外の病気が隠れている場合もあり、要注意」
長引く咳には注意が必要です。
2週間以内の咳は、風邪の可能性が高いが、2週間以上咳が続くと、なにか病気が潜んでいるかもしれない危険なサインだという。
2週間以上の咳で考えられる病気だ。
●一日中激しい咳が続くと百日咳の可能性
●胸やけや胃もたれがあると胃食道逆流症(逆流性食道炎)の可能性
●発熱、倦怠感、食欲不振があると肺炎の可能性
●鼻水が喉に落ちて咳が出る症状があると副鼻腔炎の可能性
今、マイコプラズマ肺炎が流行している。
9月29日までの1週間の1医療機関当たりの患者数が、1.64人。
2023年の同じ時期の1医療機関当たりの患者数は、0.04人だった。
1999年の統計開始以来、過去最多となっている。
マイコプラズマ肺炎の主な症状は、以下の通り。
発熱や倦怠感、そして咳が長期間続く。
秋冬に増加する傾向がある。
マイコプラズマ肺炎になった患者の年齢だ。
●0~4歳 17.8%
●5~9歳 43.5%
●10~19歳 30.9%
と子どもがかかりやすい病気だ。
ただ、子どもは軽症で済むことが多いですが、大人は重症化することもある。
風邪は発熱と同時に咳がでるケースが多いが、マイコプラズマ肺炎は発熱してから3日から5日後に、乾いた激しい咳が出はじめる。
発熱から咳までに時間差がある。
なぜ、今年マイコプラズマ肺炎が大流行しているのか?
池袋大谷クリニック 大谷義夫院長「コロナ禍のマスク生活の影響で、ここ数年、マイコプラズマ肺炎の流行が抑えられていた。その反動で今年の大流行が起きた可能性がある」「子どもから大人へ感染するので、子どもと接触する機会の多い人は、マスクをつける、アルコールで手指消毒、タオルを共有しないなどの対策が効果的。実際に、孫からマイコプラズマ肺炎に感染したという患者もいた」
のどや肺を守るための夜の習慣について、池袋大谷クリニックの大谷院長に聞いた。
寝る前に、口腔ケア。
歯みがき、舌みがきで、肺炎などの原因となる細菌の増殖を防ぐ。
寝ている時に、口閉じテープで鼻呼吸にする。
鼻毛や鼻粘膜がフィルターとなり、細菌やウイルスの体内への侵入を防ぐ。
夕食後の寝る姿勢は、左向きで寝ることがオススメ。
胃は体の左側に広がっているので、右向きで寝ると食道からのどに胃液が逆流し、咳が出やすくなる。
参照元:Yahoo!ニュース

